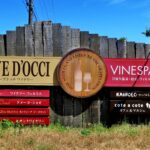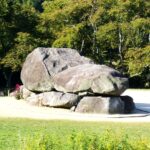東に雄大な北アルプス立山連峰を望み、北は海の幸が豊富な富山湾に面している豊かな自然に恵まれた富山市。富山城の城下町として栄えるとともに、明治頃までは市街地を流れる神通川やいたち川などの河川を利用した水運が、物流、文化交流の主要な交通路になっていたため、水の都としても知られています。富山市では、神通川の川筋の名残である松川で船による遊覧が楽しめるほか、川に沿って公園が整備され水辺は人々の憩いの場所として親しまれています。市街地は整備された近代的な町ですが、富山駅からモダンな路面電車に乗って走ると、途端に町の印象が身近になるようです。富山市街と富岩運河の水上ラインや富山地方鉄道富山港線で結ばれた神通川の河口にある岩瀬地区は北前船交易の最盛期を担った港町。 さわやかな水音に耳を澄ましながら、歴史と自然豊かな富山散策へ出かけます。
 JR富山駅から徒歩9分のところに、水と緑に恵まれた富山市中心部の名所で神通川に沿うように流れる運河が美しい風景をつくり出す富岩運河環水公園があります。蛇行した流路のため、たびたび洪水を引き起こしていた神通川を明治34年(1901)川の流れを直線化する馳越線工事を開始し、その後大正11年(1922)頃には完全に流れを移し替え、現在の神通川となりました。しかし市街地には広大な廃川地が残り、近代都市としての発展を妨げていました。そこで富山駅北から東岩瀬港の間に「富岩運河」を開削し、掘った土砂で神通川の廃川地を埋め立てる新市街地整備が行われました。富岩運河は昭和5年(1930)着工、昭和10年(1935)使用開始となりました。その際富岩運河の中央に上流と下流の水位差2.5mを調整するパナマ運河方式の中島閘門を設置し、船が運河を上り下りする際の運行の助けとなり、水路が繋がったことにより、船による資材運搬が非常に便利となりました。写真は環水公園のシンボル天門橋。橋長58m、高さ20.4m展望塔から環水公園や立山連峰が一望できます。
JR富山駅から徒歩9分のところに、水と緑に恵まれた富山市中心部の名所で神通川に沿うように流れる運河が美しい風景をつくり出す富岩運河環水公園があります。蛇行した流路のため、たびたび洪水を引き起こしていた神通川を明治34年(1901)川の流れを直線化する馳越線工事を開始し、その後大正11年(1922)頃には完全に流れを移し替え、現在の神通川となりました。しかし市街地には広大な廃川地が残り、近代都市としての発展を妨げていました。そこで富山駅北から東岩瀬港の間に「富岩運河」を開削し、掘った土砂で神通川の廃川地を埋め立てる新市街地整備が行われました。富岩運河は昭和5年(1930)着工、昭和10年(1935)使用開始となりました。その際富岩運河の中央に上流と下流の水位差2.5mを調整するパナマ運河方式の中島閘門を設置し、船が運河を上り下りする際の運行の助けとなり、水路が繋がったことにより、船による資材運搬が非常に便利となりました。写真は環水公園のシンボル天門橋。橋長58m、高さ20.4m展望塔から環水公園や立山連峰が一望できます。
 しかし物流は船運からトラック輸送に代わり、昭和60年以降は都市の水辺空間として再生され、都心のオアシスとして親しまれていて、スターバックスやミシュランガイドにも掲載されたフレンチレストラン、「アートとデザインをつなぐ」美術館の富山県美術館などがあります。写真は水辺空間に溶け込み、「世界一美しい」と言われるスターバックス。
しかし物流は船運からトラック輸送に代わり、昭和60年以降は都市の水辺空間として再生され、都心のオアシスとして親しまれていて、スターバックスやミシュランガイドにも掲載されたフレンチレストラン、「アートとデザインをつなぐ」美術館の富山県美術館などがあります。写真は水辺空間に溶け込み、「世界一美しい」と言われるスターバックス。
 南向きに建てられたガラス張りの窓からは公園の象徴である運河が一望できます。
南向きに建てられたガラス張りの窓からは公園の象徴である運河が一望できます。
 都心のオアシス「富岩運河環水公園」から港町「岩瀬」までは、富岩水上ラインで環水公園を飛び出し、爽やかな風を感じながら約60分の運河クルーズが楽しめます。中島閘門での水位差約2.5mの迫力ある「水のエレベーター」を体験して港町岩瀬へ。船は環境にやさしいソーラー船「kansui」と「fugan」「sora」、電気ボート「もみじ」が案内してくれます。
都心のオアシス「富岩運河環水公園」から港町「岩瀬」までは、富岩水上ラインで環水公園を飛び出し、爽やかな風を感じながら約60分の運河クルーズが楽しめます。中島閘門での水位差約2.5mの迫力ある「水のエレベーター」を体験して港町岩瀬へ。船は環境にやさしいソーラー船「kansui」と「fugan」「sora」、電気ボート「もみじ」が案内してくれます。
 環水公園から約7km、富岩水上ライン乗降場に建つ岩瀬カナル会館は、運河沿いにある観光施設。特産品が買えるほか、サンタフェやテルミエで食事もできます。デッキから岩瀬運河の眺めを楽しめます。運河には漁船やモーターボートが停泊し、運河沿い(写真中央左下)に「古志の人魚」とある人魚の銅像が、なぜか海に背を向けて佇んでいます。
環水公園から約7km、富岩水上ライン乗降場に建つ岩瀬カナル会館は、運河沿いにある観光施設。特産品が買えるほか、サンタフェやテルミエで食事もできます。デッキから岩瀬運河の眺めを楽しめます。運河には漁船やモーターボートが停泊し、運河沿い(写真中央左下)に「古志の人魚」とある人魚の銅像が、なぜか海に背を向けて佇んでいます。
 運河に架かる岩瀬橋と赤い欄干の大漁橋の間は水辺のプロムナードとなっていて、海からの心地よい風と潮の香りを楽しみながら散策できます。大漁橋方向に向かって左手が岩瀬地区です。
運河に架かる岩瀬橋と赤い欄干の大漁橋の間は水辺のプロムナードとなっていて、海からの心地よい風と潮の香りを楽しみながら散策できます。大漁橋方向に向かって左手が岩瀬地区です。
 日本遺産認定『荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~』と荒波を越え、動く総合商社として巨万の富を生み、岩瀬に繁栄をもたらした北前船の寄港地 船主集落“岩瀬地区”。江戸初期から日本海を行き来する北前航路が生まれ、江戸期から明治期にかけて日本海沿岸地域には廻船問屋が多く営まれていました。神通川河口の港町である岩瀬は、江戸前期の寛文年間(約320年前)におよそ千戸がひしめき合う一大寄港地で、加賀藩120万石の領地で御蔵があったこともあり北前船で米や木材などを瀬戸内・畿内に運ぶ役割を担っていましたが、幕末になると北海道に盛んに進出します。当時から評判が高かった越中の米を北海道に運び、ニシン粕や昆布を持ち帰って販売しました。当時、北海道と本州の物価の差は大きく、大阪と往復するよりも利益ははるかに大きかったので、ここに目をつけた越中商人は、主に北海道との間を往復するようになります。航海のたびに利益が倍になることから「バイ船」と呼ばれた北前船の交易で、江戸時代から明治時代にかけて大いに栄えたのです。写真は岩瀬大町公園に置かれた北前船
日本遺産認定『荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~』と荒波を越え、動く総合商社として巨万の富を生み、岩瀬に繁栄をもたらした北前船の寄港地 船主集落“岩瀬地区”。江戸初期から日本海を行き来する北前航路が生まれ、江戸期から明治期にかけて日本海沿岸地域には廻船問屋が多く営まれていました。神通川河口の港町である岩瀬は、江戸前期の寛文年間(約320年前)におよそ千戸がひしめき合う一大寄港地で、加賀藩120万石の領地で御蔵があったこともあり北前船で米や木材などを瀬戸内・畿内に運ぶ役割を担っていましたが、幕末になると北海道に盛んに進出します。当時から評判が高かった越中の米を北海道に運び、ニシン粕や昆布を持ち帰って販売しました。当時、北海道と本州の物価の差は大きく、大阪と往復するよりも利益ははるかに大きかったので、ここに目をつけた越中商人は、主に北海道との間を往復するようになります。航海のたびに利益が倍になることから「バイ船」と呼ばれた北前船の交易で、江戸時代から明治時代にかけて大いに栄えたのです。写真は岩瀬大町公園に置かれた北前船
 明治6年(1873)に大火があり、約千戸あった家屋の内、半数以上の約650戸が焼失しましたが、当時廻船問屋業が全盛を迎えており、それを痛手とせず財力によって、より重厚な岩瀬独自の家屋形式「東岩瀬廻船問屋型町家」として再建されました。廻船問屋の家屋の多くは、江戸時代から変わらないという岩瀬大町・新川町通り(旧北国街道)沿いを表構えにし河岸を背に建てられ、間口が広く、豪壮ながら繊細な装飾が施された家々に注目です。また家々の出格子は全国的にも珍しい竹の簾をはめ込んだもので「簀虫籠(スムシコ)」と呼ばれています。広い通り全体に優しい佇まいを感じさせてくれ、道の両側に整然と立つ並ぶ町家が、統一感のある端正な町並みをつくり出しています。
明治6年(1873)に大火があり、約千戸あった家屋の内、半数以上の約650戸が焼失しましたが、当時廻船問屋業が全盛を迎えており、それを痛手とせず財力によって、より重厚な岩瀬独自の家屋形式「東岩瀬廻船問屋型町家」として再建されました。廻船問屋の家屋の多くは、江戸時代から変わらないという岩瀬大町・新川町通り(旧北国街道)沿いを表構えにし河岸を背に建てられ、間口が広く、豪壮ながら繊細な装飾が施された家々に注目です。また家々の出格子は全国的にも珍しい竹の簾をはめ込んだもので「簀虫籠(スムシコ)」と呼ばれています。広い通り全体に優しい佇まいを感じさせてくれ、道の両側に整然と立つ並ぶ町家が、統一感のある端正な町並みをつくり出しています。
 岩瀬は江戸時代に加賀藩主が参勤交代の際に通る浜街道で、通りで現在見られる古い建物の多くは北前航路が最盛期の明治初期に建てられた米田家、森家、馬場家、佐渡家、宮城家の岩瀬五大家などの廻船問屋が建ち並ぶ歴史的な街並みです。そんな南北に500mほど伸びる通りの岩瀬地区が今古くて新しい表情をもつ町並みに変化してきています。
岩瀬は江戸時代に加賀藩主が参勤交代の際に通る浜街道で、通りで現在見られる古い建物の多くは北前航路が最盛期の明治初期に建てられた米田家、森家、馬場家、佐渡家、宮城家の岩瀬五大家などの廻船問屋が建ち並ぶ歴史的な街並みです。そんな南北に500mほど伸びる通りの岩瀬地区が今古くて新しい表情をもつ町並みに変化してきています。
岩瀬運河沿いから小路へ入った岩瀬大町新川町通りへ向かう閑静な場所にあるのが「磯料理 松月」です。創業明治44年(1911)、岩瀬の浜に、北前船が往来していた頃からの“浜の旦那衆”に引き立てられて歴史を重ねてきました。かつて廻船問屋が軒を連ねていた街に建つ土塀と黒瓦が重厚な風格のある建物で、玄関に掲げられた二枚の看板は、北前船の舟板で作られたといい、港町の歴史が刻まれています。自慢の磯料理は、眼前の富山湾から揚がる旬の地魚を活かし、御用邸料理人の系譜を受け継ぐ料理法にて仕上げたもの。中でも名産の白エビ料理、名物「福団子」は手むきの白エビをすって団子にしたもので、一串に約200尾もの白エビ使われている松月の真髄ともいえる一品です。
 岩瀬大町・新川通りのちょうど入口にあたる角地でのれんを出すのは、老舗の総菜屋「野村商店」。魚の仲卸をやっていたという祖父が戦後間もないころに創業し60年余り、地元で愛されている看板商品の昆布巻きは、1日半かけて手作りしています。昆布はほろりと柔らかく、中のニシンにまでしっかりと染みた味はまろやかです。昆布もニシンも北前船が運んだ食文化。とりわけ富山では、全国でも有数の昆布の消費地となるほどに、深く暮らしに根付いています。
岩瀬大町・新川通りのちょうど入口にあたる角地でのれんを出すのは、老舗の総菜屋「野村商店」。魚の仲卸をやっていたという祖父が戦後間もないころに創業し60年余り、地元で愛されている看板商品の昆布巻きは、1日半かけて手作りしています。昆布はほろりと柔らかく、中のニシンにまでしっかりと染みた味はまろやかです。昆布もニシンも北前船が運んだ食文化。とりわけ富山では、全国でも有数の昆布の消費地となるほどに、深く暮らしに根付いています。
新しい岩瀬を知るならまずは、桝田酒造店が造る満寿泉のアンテナショップ的な存在「満寿泉 沙石」へ。廻船問屋の宮城家を解体・再生した建物で、令和元年にオープンした満寿泉の立ち飲みバー、すがすがしい和の美を感じる建物です。店内の杉の大木が目を引きます。南砺市の井波別院瑞泉寺境内で落雷を受けたというスギのたたずまいが日本酒バーによく合います。
 立ち飲みスタイルの店で約100種の日本酒「満寿泉」が冷蔵庫に入り、唎酒は試飲用木桝(220円)を購入して冷蔵庫の中から好きなお酒を選び、1種200~500円で飲んだ分だけ支払う形の“セルフ唎酒”と自由に飲み比べできる(30分2000円~)の2つのシステムがあり、ここでしか飲めない酒も多い。
立ち飲みスタイルの店で約100種の日本酒「満寿泉」が冷蔵庫に入り、唎酒は試飲用木桝(220円)を購入して冷蔵庫の中から好きなお酒を選び、1種200~500円で飲んだ分だけ支払う形の“セルフ唎酒”と自由に飲み比べできる(30分2000円~)の2つのシステムがあり、ここでしか飲めない酒も多い。
 森家土蔵群内に店を構える「酒商 田尻本店」は築167年の元米蔵をリノベーションし、1500種以上の日本酒とワインをそろえる酒販店。日本酒は「満寿泉」「林」「曙」「菊姫」など富山や北陸の蔵元を中心に、流行や知名度にとらわれることなく、店主が厳選した清酒のみを蔵元から直接仕入れています。紫外線を遮断したウォークインセラーにずらりと商品が並ぶ様子は圧巻です。
森家土蔵群内に店を構える「酒商 田尻本店」は築167年の元米蔵をリノベーションし、1500種以上の日本酒とワインをそろえる酒販店。日本酒は「満寿泉」「林」「曙」「菊姫」など富山や北陸の蔵元を中心に、流行や知名度にとらわれることなく、店主が厳選した清酒のみを蔵元から直接仕入れています。紫外線を遮断したウォークインセラーにずらりと商品が並ぶ様子は圧巻です。
岩瀬北前船主五大家の筆頭で北陸五大北前船主のひとつに挙げられる馬場家は、屋号は「道正屋(どうしょうや)」で、道正村より移り住んだことに由来します。「旧馬場家住宅」の主屋や蔵の一部が2021年から公開されています。住宅主屋は当家隆盛の基礎を築いた七代当主久兵衛が建てたと伝えられ、明治6年(1873)の大火後に一部の部材を再利用して建てられたと考えられ、随所から往時の繁栄ぶりがうかがえます。岩瀬大町通りと旧神通川を突き抜ける広大な敷地に、建坪230坪の主屋、三階建ての前蔵・壱番蔵・弐番蔵・味噌蔵・二千石の広大な米蔵があり、西門及び西塀が現存し、廻船業が盛んであった当時の面影を残しています。
 東岩瀬の中でも最大規模の住宅で、内部には全面高い天窓から白壁を伝って光が降り注ぐトオリニワ(屋内通路)と呼ぶ長さ30m、幅2.7mもの土間通路があります。暖簾には馬場家の家紋「隅切角一地紙」が染め抜かれています。
東岩瀬の中でも最大規模の住宅で、内部には全面高い天窓から白壁を伝って光が降り注ぐトオリニワ(屋内通路)と呼ぶ長さ30m、幅2.7mもの土間通路があります。暖簾には馬場家の家紋「隅切角一地紙」が染め抜かれています。
 江戸時代の形に復元した豪壮な梁が見える33畳もの商取引の間オイ(広間)。中央に小川に見立てた畳の模様敷きが。正面に見えるのが江戸時代の蔵を改造した前蔵で、町の延焼を防ぐ役割がありました。
江戸時代の形に復元した豪壮な梁が見える33畳もの商取引の間オイ(広間)。中央に小川に見立てた畳の模様敷きが。正面に見えるのが江戸時代の蔵を改造した前蔵で、町の延焼を防ぐ役割がありました。
 トオリニワを抜けて庭園に出ると、海に近い場所特有の明るさに包まれます。主屋と海からの玄関口である西門をつなぐ通路で、昭和初期まで家の裏側は神通川に面しており、北海道から海を渡ってきた船と蔵との間で、荷物の搬出入がすぐに行えていました。かつては大八車が行き来したのでしょう。そのため大きな廻船問屋の家はいずれも大町通りの西側(川側)に建てられていました。北側に蔵が並びます。
トオリニワを抜けて庭園に出ると、海に近い場所特有の明るさに包まれます。主屋と海からの玄関口である西門をつなぐ通路で、昭和初期まで家の裏側は神通川に面しており、北海道から海を渡ってきた船と蔵との間で、荷物の搬出入がすぐに行えていました。かつては大八車が行き来したのでしょう。そのため大きな廻船問屋の家はいずれも大町通りの西側(川側)に建てられていました。北側に蔵が並びます。
 明治時代に建造された壱番蔵・弐番蔵・味噌蔵には唐獅子に牡丹など、前蔵よりも立派な彫刻が施されています。※非公開エリア
明治時代に建造された壱番蔵・弐番蔵・味噌蔵には唐獅子に牡丹など、前蔵よりも立派な彫刻が施されています。※非公開エリア
 かつて旧馬場家の米蔵だった場所が、リノベーションを経て、チェコ出身の醸造家によるクラフトビールの醸造とパブの営業をする「KOBO Brew Pub」に生まれ変わりました。伝統的なチェコの醸造スタイルを用いて造る、黒ビール、エール、ラガービールをはじめ、近くで日本酒を醸す蔵元の酒粕を使ったビールや富山市名産の「呉羽梨」のシロップを使ったビールなど、地元の食材を取り入れ、自由な感性で仕上げるクラフトビールも人気で、常時9種類ほどをラインナップしています。いろんな味を楽しみたい人には、4種類を飲み比べできるテイスティングセットがおすすめです。店内では、スロバキア伝統のソーセージなどのおつまみと共に飲み比べが楽しめます。
かつて旧馬場家の米蔵だった場所が、リノベーションを経て、チェコ出身の醸造家によるクラフトビールの醸造とパブの営業をする「KOBO Brew Pub」に生まれ変わりました。伝統的なチェコの醸造スタイルを用いて造る、黒ビール、エール、ラガービールをはじめ、近くで日本酒を醸す蔵元の酒粕を使ったビールや富山市名産の「呉羽梨」のシロップを使ったビールなど、地元の食材を取り入れ、自由な感性で仕上げるクラフトビールも人気で、常時9種類ほどをラインナップしています。いろんな味を楽しみたい人には、4種類を飲み比べできるテイスティングセットがおすすめです。店内では、スロバキア伝統のソーセージなどのおつまみと共に飲み比べが楽しめます。
 西門・西塀は北前船の時代よりも後のものと考えられ、裏門であるが、表門のような上質な構えになっています。
西門・西塀は北前船の時代よりも後のものと考えられ、裏門であるが、表門のような上質な構えになっています。
 旧馬場家住宅の隣が同じく岩瀬五大家のひとつ、旧森家です。「北前船廻船問屋 森家」は、明治11年(1876)建築の北前船船主・廻船問屋邸宅。四十物屋仙右エ門と言い、通称あいせんと呼ばれ文政の頃より北前船で栄えた東岩瀬の廻船問屋の様式を残している屋敷です。特徴は、当地から積出す船荷のため玄関から裏の船着き場まで、通り庭(土間廊下)が通じ、表から母屋・台所・土蔵が並びます。母屋のオイには炉が切られその部屋は天井まで吹き抜けの構造で梁が井形に走り(枠の内)明かり窓が取ってあります。ミセは帳場で二階が番頭の居間になっています。板戸には屋久杉、梁には能登産黒松など全国から取り寄せた材料を使用。吹き抜けの木組み、土蔵の鏝絵などの意匠が随所にみられ、当時の繁栄がうかがえる。建坪80.2坪、延坪112.5坪あります。※長期休館中
旧馬場家住宅の隣が同じく岩瀬五大家のひとつ、旧森家です。「北前船廻船問屋 森家」は、明治11年(1876)建築の北前船船主・廻船問屋邸宅。四十物屋仙右エ門と言い、通称あいせんと呼ばれ文政の頃より北前船で栄えた東岩瀬の廻船問屋の様式を残している屋敷です。特徴は、当地から積出す船荷のため玄関から裏の船着き場まで、通り庭(土間廊下)が通じ、表から母屋・台所・土蔵が並びます。母屋のオイには炉が切られその部屋は天井まで吹き抜けの構造で梁が井形に走り(枠の内)明かり窓が取ってあります。ミセは帳場で二階が番頭の居間になっています。板戸には屋久杉、梁には能登産黒松など全国から取り寄せた材料を使用。吹き抜けの木組み、土蔵の鏝絵などの意匠が随所にみられ、当時の繁栄がうかがえる。建坪80.2坪、延坪112.5坪あります。※長期休館中
 姿のよい松に迎えられる「つりや 東岩瀬」は氷見漁港で江戸時代から続く“釣屋魚問屋”が富山の魚食文化をはじめ、食の楽しさを発信する場所をと、昭和初期に診療所として使われていた建物をリノベーションし、2階に1日1組の宿、1階に物販・喫茶スペースをオープン。物販では、魚介の燻製やオイル漬けなど自社製品をはじめ国内外問わず丁寧に作られる調味料やさまざまな食材を扱っています。
姿のよい松に迎えられる「つりや 東岩瀬」は氷見漁港で江戸時代から続く“釣屋魚問屋”が富山の魚食文化をはじめ、食の楽しさを発信する場所をと、昭和初期に診療所として使われていた建物をリノベーションし、2階に1日1組の宿、1階に物販・喫茶スペースをオープン。物販では、魚介の燻製やオイル漬けなど自社製品をはじめ国内外問わず丁寧に作られる調味料やさまざまな食材を扱っています。
 斜め向かいには明治26年(1893)、北前船で北海道へ渡り、当時開拓民や屯田兵で人口が急増した旭川で1500石の酒造で創業した銘酒「満寿泉」で知られる蔵元・桝田酒造店。能登杜氏が、上品な香りと深い味わいにこだわって造る酒は、富山の旬の幸とも相性抜群。日本酒をウイスキー樽やワイン樽で熟成するなど、新たな日本酒造りにも挑戦しています。
斜め向かいには明治26年(1893)、北前船で北海道へ渡り、当時開拓民や屯田兵で人口が急増した旭川で1500石の酒造で創業した銘酒「満寿泉」で知られる蔵元・桝田酒造店。能登杜氏が、上品な香りと深い味わいにこだわって造る酒は、富山の旬の幸とも相性抜群。日本酒をウイスキー樽やワイン樽で熟成するなど、新たな日本酒造りにも挑戦しています。
 大町・新川通りの南辺に、明治時代の大火を免れた、かつて加賀藩の土蔵だった建物の食堂が「食堂 天保」です。ラーメンやカレーライスなどがそろう大衆食堂ですが、気軽に富山の海の幸を楽しめるお店でもあります。名物は“富山湾の宝石”と呼ばれる白エビを使った料理。人気の白えびは海鮮丼でいただきます。
大町・新川通りの南辺に、明治時代の大火を免れた、かつて加賀藩の土蔵だった建物の食堂が「食堂 天保」です。ラーメンやカレーライスなどがそろう大衆食堂ですが、気軽に富山の海の幸を楽しめるお店でもあります。名物は“富山湾の宝石”と呼ばれる白エビを使った料理。人気の白えびは海鮮丼でいただきます。
 海鮮丼には白エビ、カニ、甘エビ、マグロなど10種以上のネタが盛られます。残念ながら今は白エビが不漁とのことで白エビコロッケがありません。春の訪れとともに始まる富山湾の白エビ漁。今や高級食材として広く知られ、刺身はもちろんさまざまな料理にも利用される白エビは豊かな海の象徴であり、富山県ならではの美食。透明感のある白エビは、世界的にも珍しい品種で、体長は約6~7cmで、本来は無色透明。水揚げ直後はキラキラと輝き、“富山湾の宝石”と称されています。
海鮮丼には白エビ、カニ、甘エビ、マグロなど10種以上のネタが盛られます。残念ながら今は白エビが不漁とのことで白エビコロッケがありません。春の訪れとともに始まる富山湾の白エビ漁。今や高級食材として広く知られ、刺身はもちろんさまざまな料理にも利用される白エビは豊かな海の象徴であり、富山県ならではの美食。透明感のある白エビは、世界的にも珍しい品種で、体長は約6~7cmで、本来は無色透明。水揚げ直後はキラキラと輝き、“富山湾の宝石”と称されています。
 帰路は富山地方鉄道富山港線の岩瀬浜駅から富山駅に戻るので、途中岩瀬大町新川町通りの北端、富山港展望台へ。船乗りたちの信仰を集めた金刀比羅社の境内の常夜灯をモデルにした昭和61年(1986)完成の展望台。地上から24.85mの高さがあり、100段の階段を上って展望台に着くと、富山湾と岩瀬の町が眼下に。そして反対側を向くと晴れた日には富山湾越しにそびえる雄大な立山連峰が一望でき、海と山、二つの美しい風景が一度に楽しめます。越中の北前船にとって、海から望む立山の姿は格別だったに違いなく、冒険を恐れず、あらたな世界に帆を張ってゆく、北前船のスピリットを今も感じることができる岩瀬の旅です。
帰路は富山地方鉄道富山港線の岩瀬浜駅から富山駅に戻るので、途中岩瀬大町新川町通りの北端、富山港展望台へ。船乗りたちの信仰を集めた金刀比羅社の境内の常夜灯をモデルにした昭和61年(1986)完成の展望台。地上から24.85mの高さがあり、100段の階段を上って展望台に着くと、富山湾と岩瀬の町が眼下に。そして反対側を向くと晴れた日には富山湾越しにそびえる雄大な立山連峰が一望でき、海と山、二つの美しい風景が一度に楽しめます。越中の北前船にとって、海から望む立山の姿は格別だったに違いなく、冒険を恐れず、あらたな世界に帆を張ってゆく、北前船のスピリットを今も感じることができる岩瀬の旅です。
 富山地方鉄道富山港線(富山ライトレール)は、JR西日本から引き継いだ富山港線に新たに5つの電停を設置し、併用軌道を新設して、平成18年に開業した日本初の本格的LRTとして開業。ドイツのブレーメン型超低床市電車を元につくられたTLRO600形の路面電車が2006年から運行され、富山駅と岩瀬浜間7.6㎞を結んでいます。PortとTramを組み合わせたポートラムが愛称。外観の白色は立山の新雪をイメージし、街中をすべるように走っていくのが楽しい。
富山地方鉄道富山港線(富山ライトレール)は、JR西日本から引き継いだ富山港線に新たに5つの電停を設置し、併用軌道を新設して、平成18年に開業した日本初の本格的LRTとして開業。ドイツのブレーメン型超低床市電車を元につくられたTLRO600形の路面電車が2006年から運行され、富山駅と岩瀬浜間7.6㎞を結んでいます。PortとTramを組み合わせたポートラムが愛称。外観の白色は立山の新雪をイメージし、街中をすべるように走っていくのが楽しい。
 座席は、連接部はロングシート、その他はボックスシートを採用。ボックスシートは通路を挟んで2人掛けシートと1.5人掛けシートをが並ぶ変則的な配置で、1.5人掛けシートを向かい合わせに配置した区画はボックス1区画につき着席定員3名でカウントされています。2015年3月の北陸新幹線金沢延伸開業に合わせ、シートモケットの張替えが行われた。
座席は、連接部はロングシート、その他はボックスシートを採用。ボックスシートは通路を挟んで2人掛けシートと1.5人掛けシートをが並ぶ変則的な配置で、1.5人掛けシートを向かい合わせに配置した区画はボックス1区画につき着席定員3名でカウントされています。2015年3月の北陸新幹線金沢延伸開業に合わせ、シートモケットの張替えが行われた。
 25分の乗車で富山駅に到着です。
25分の乗車で富山駅に到着です。
「心ときめく時を求めてアートとグルメでめぐる、富山の旅」はこちらhttps://wakuwakutrip.com/archives/19203