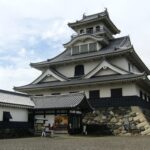戦災で天守閣は焼失したといえ、そこは御三家筆頭・尾張徳川家の居城、名古屋城。隅櫓が現存し、加藤清正が築いた天守台が姿を留めるなど、実は見どころ豊富な城内に、2018年本丸御殿が復元されました。金シャチをいただく名古屋城天守は木造復元計画と耐震工事で閉館していますが、名古屋城の目の前に広がるグルメスポット「金シャチ横丁」で名古屋グルメを味わい、名古屋城に残る歴史遺産を探して歩きます。
 約400年前の姿を取り戻した本丸御殿は、初代尾張藩主の住居・政庁として使用するため、慶長20年(1615)に建てられましたが、徳川義直は、元和6年(1620)に二の丸御殿へ移り、後に将軍専用の宿館となりました。寛永3年(1626)には、2代将軍・秀忠が上洛の折に名古屋城本丸御殿に滞在しています。総面積は約3100㎡、ヒノキ造り(一部杉造り)、杮葺きの建物13棟が連なり、部屋数は30を超える平屋建ての建物です。昭和20年(1945)の空襲により焼失しましたが、平成21年(2009)から復元工事を開始し、平成30年(2018)、約10年かかって復元された本丸御殿は、京都二条城の本丸御殿と並ぶ武家風書院造りの双璧と言われます。
約400年前の姿を取り戻した本丸御殿は、初代尾張藩主の住居・政庁として使用するため、慶長20年(1615)に建てられましたが、徳川義直は、元和6年(1620)に二の丸御殿へ移り、後に将軍専用の宿館となりました。寛永3年(1626)には、2代将軍・秀忠が上洛の折に名古屋城本丸御殿に滞在しています。総面積は約3100㎡、ヒノキ造り(一部杉造り)、杮葺きの建物13棟が連なり、部屋数は30を超える平屋建ての建物です。昭和20年(1945)の空襲により焼失しましたが、平成21年(2009)から復元工事を開始し、平成30年(2018)、約10年かかって復元された本丸御殿は、京都二条城の本丸御殿と並ぶ武家風書院造りの双璧と言われます。
 厚さ約3mmの杉の薄板を張り合わせ施工したこけら葺き屋根と唐破風屋根を戴く車寄は、将軍や藩主が利用できる入口。見学でもここからは入れず、中之口部屋横の入口から中へ。かつての来客は、藩主との謁見まで玄関の一之間、または二之間で控えました。両部屋とも藩主の威厳を示す障壁画の「竹林豹虎図」が描かれ、虎の間と呼ばれました。当時日本の本物はおらず書物や毛皮を参考に描かれています。
厚さ約3mmの杉の薄板を張り合わせ施工したこけら葺き屋根と唐破風屋根を戴く車寄は、将軍や藩主が利用できる入口。見学でもここからは入れず、中之口部屋横の入口から中へ。かつての来客は、藩主との謁見まで玄関の一之間、または二之間で控えました。両部屋とも藩主の威厳を示す障壁画の「竹林豹虎図」が描かれ、虎の間と呼ばれました。当時日本の本物はおらず書物や毛皮を参考に描かれています。
 中に入ると廊下沿いに大小の広間が並び、それぞれに障壁画が描かれていて日本画の美術館のようです。将軍家の御用絵師として名を馳せた狩野貞信や狩野探幽ら狩野派の絵師によって、御殿の襖や天井板には異なる題材の絵が部屋ごとに描かれています。写真は表書院三之間でジャコウネコが描かれています。
中に入ると廊下沿いに大小の広間が並び、それぞれに障壁画が描かれていて日本画の美術館のようです。将軍家の御用絵師として名を馳せた狩野貞信や狩野探幽ら狩野派の絵師によって、御殿の襖や天井板には異なる題材の絵が部屋ごとに描かれています。写真は表書院三之間でジャコウネコが描かれています。
 名古屋城がユニークなのは、昭和20年(1945)まで現存していたため写真や実測図が豊富に残り、忠実に復元できる点です。玄関に始まり、謁見の間である表書院、藩主が私的な対面や宴席に使う対面所と、奥へ進むにつれて部屋の雰囲気も変わります。部屋の格式で障壁画の絵柄が変化し、獣から花鳥、見世物、田植えなど当時の庶民の暮らしを描いた風俗図へと。部屋によって風景がガラリと変わります。藩主と来客が公式の謁見を行う場である表書院。藩主は一段高い上段之間に座し、来客はその地位によって一之間、二之間、三之間のいずれかに通されました。藩主と直接謁見できたのは一之間と二之間。写真は表書院北面。手前が一之間の桜花雉子図、白雉という稀でめでたい鳥が描かれていて、天井は簡素な竿縁天井。奥の上段之間は藩主の間
名古屋城がユニークなのは、昭和20年(1945)まで現存していたため写真や実測図が豊富に残り、忠実に復元できる点です。玄関に始まり、謁見の間である表書院、藩主が私的な対面や宴席に使う対面所と、奥へ進むにつれて部屋の雰囲気も変わります。部屋の格式で障壁画の絵柄が変化し、獣から花鳥、見世物、田植えなど当時の庶民の暮らしを描いた風俗図へと。部屋によって風景がガラリと変わります。藩主と来客が公式の謁見を行う場である表書院。藩主は一段高い上段之間に座し、来客はその地位によって一之間、二之間、三之間のいずれかに通されました。藩主と直接謁見できたのは一之間と二之間。写真は表書院北面。手前が一之間の桜花雉子図、白雉という稀でめでたい鳥が描かれていて、天井は簡素な竿縁天井。奥の上段之間は藩主の間
 藩主が坐した上段之間は一段高く設えられれ、違棚や高天井が格式を示しています。天井は格式の高い折上小組格天井に、藩主が背にした壁には、尾張藩の繁栄を象徴するように、力強く幹を伸ばす松が描かれています。
藩主が坐した上段之間は一段高く設えられれ、違棚や高天井が格式を示しています。天井は格式の高い折上小組格天井に、藩主が背にした壁には、尾張藩の繁栄を象徴するように、力強く幹を伸ばす松が描かれています。
 ここからさらに奥に進むと、藩主が側近や親族と私的な対面や宴席に用いた対面所へ至る。上段之間は表書院よりもさらに格式高く、天井は黒漆塗で金箔を押した黒漆二重折上げ小組格天井に、釘隠しや欄間の装飾も緻密になっています。青い七宝細工を使った引手金具も目を引きます。食事を運びやすいようにすぐそばに下御膳所が設けられています。
ここからさらに奥に進むと、藩主が側近や親族と私的な対面や宴席に用いた対面所へ至る。上段之間は表書院よりもさらに格式高く、天井は黒漆塗で金箔を押した黒漆二重折上げ小組格天井に、釘隠しや欄間の装飾も緻密になっています。青い七宝細工を使った引手金具も目を引きます。食事を運びやすいようにすぐそばに下御膳所が設けられています。
 初代藩主・義直と春姫との婚儀も対面所で行われたとか。そのため床の間には徳川家にゆかりの深い京都・愛宕山を描いた障壁画を、また壁面には春姫の故郷・和歌山の風景が描かれていて、藩主がよりくつろげる趣になっています。写真は対面所・次之間
初代藩主・義直と春姫との婚儀も対面所で行われたとか。そのため床の間には徳川家にゆかりの深い京都・愛宕山を描いた障壁画を、また壁面には春姫の故郷・和歌山の風景が描かれていて、藩主がよりくつろげる趣になっています。写真は対面所・次之間
 下御善所は、長囲炉裏が備えられており、料理の配膳や温め直しのための建物だと考えられています。天井には煙出しがあります。
下御善所は、長囲炉裏が備えられており、料理の配膳や温め直しのための建物だと考えられています。天井には煙出しがあります。
 壁一面に金箔を貼った鷺之廊下。対面所と上洛殿を結ぶための廊下で、寛永11年(1634)に上洛殿とともに増築されました。長押の上まで障壁画が描かれるのが寛永期の特徴です。将軍や藩主はここを通り上洛殿へ向かいました。
壁一面に金箔を貼った鷺之廊下。対面所と上洛殿を結ぶための廊下で、寛永11年(1634)に上洛殿とともに増築されました。長押の上まで障壁画が描かれるのが寛永期の特徴です。将軍や藩主はここを通り上洛殿へ向かいました。
 極めつけの上洛殿は、寛永11年(1634)に三代将軍家光の上洛に合わせて増築された最奥部の御成御殿です。江戸時代は御書院・御白書院と呼ばれ、本丸御殿で最も格式の高い建物です。天井には板絵が飾られ、部屋の境には極彩色の彫刻欄間がはめ込まれり絢爛ぶりで、飾り金具も華やかな彩りを添えています。特に家光の御座所となった上段の間は、息をのむほどの空間。江戸初期の絵師狩野探幽による水墨画「雪中梅竹鳥図」「帝鑑図」に囲まれた贅を極めた荘厳な空間に圧倒されます。
極めつけの上洛殿は、寛永11年(1634)に三代将軍家光の上洛に合わせて増築された最奥部の御成御殿です。江戸時代は御書院・御白書院と呼ばれ、本丸御殿で最も格式の高い建物です。天井には板絵が飾られ、部屋の境には極彩色の彫刻欄間がはめ込まれり絢爛ぶりで、飾り金具も華やかな彩りを添えています。特に家光の御座所となった上段の間は、息をのむほどの空間。江戸初期の絵師狩野探幽による水墨画「雪中梅竹鳥図」「帝鑑図」に囲まれた贅を極めた荘厳な空間に圧倒されます。
 写真は上洛殿一之間北東面
写真は上洛殿一之間北東面