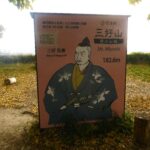栃木市は江戸時代に巴波川の舟運で栄えた商都で、現在もその歴史を偲ばせる蔵の街として知られています。そんな物資だけでなく、人の交流も盛んでだったであろう商都として栄えた蔵の町・栃木の人々が、心の拠りどころとした二つの霊場、天下泰平を祈る太平山神社と坂東三十三観音霊場の札所・出流山満願寺をめぐります。中心部の昔町風情と打って変わって、郊外は豊かな自然と歴史が調和します。江戸からも講を組んで大勢の人が訪れたというこの地の何に一体引き付けられたのだろうか、その魅力を探しに出かけます。
まず向かう太平山神社は、市の中心部から西へ5km、平地から突如聳える標高345mの太平山山頂に鎮まる42座の神様を祀る神社です。古来より太平山をご神体とし、天長4年(827)下野国出身の慈覚大師円仁が天皇の勅額を奉じた社。「全ての神々この山に有り全ての御神徳この山より始まる」と言われるパワースポットです。車で近くまで行けるのですが、桜まつり開催期間中は太平山遊覧道路が一方通行となるため、迂回ルートは2通り。ひとつは桜のトンネルの遊覧道路から山頂・謙信平へ向かうコース。錦着山を過ぎ永野川を渡ると太平山山頂に向かう遊覧道路となります。4月初旬から中旬には、約2kmに及ぶ桜のトンネルになります。
 迂回ルートの二つ目は、あじさい坂駐車場から徒歩で山頂の大平山神社を目指します。あじさい坂駐車場に車を停めて麓から随身門に至る約1000段の石段「厄除けの石段」・あじさい坂を登るほうがゴールした時の感慨も深いものがあります。石段の両側に、西洋アジサイや額アジサイ、山アジサイなど約2500種株が植えられていて、6月下旬から7月上旬には一斉に咲き競います。石段はこの山で産出する石を使った「野面積み」で、信徒の労力と寄進によるもので、雨の日は黒く光り格別に美しい。約30分の行程です。
迂回ルートの二つ目は、あじさい坂駐車場から徒歩で山頂の大平山神社を目指します。あじさい坂駐車場に車を停めて麓から随身門に至る約1000段の石段「厄除けの石段」・あじさい坂を登るほうがゴールした時の感慨も深いものがあります。石段の両側に、西洋アジサイや額アジサイ、山アジサイなど約2500種株が植えられていて、6月下旬から7月上旬には一斉に咲き競います。石段はこの山で産出する石を使った「野面積み」で、信徒の労力と寄進によるもので、雨の日は黒く光り格別に美しい。約30分の行程です。
 序盤から息を切れますが、樹齢1000年を超える杉の御神木など坂の途中の見どころも多く、楽しみながら上ると、随身門が迎えてくれます。享保8年(1723)徳川吉宗の寄進により建立。前に左右大臣、後に仁王の守護神を配したもので太平山が寺院の山として栄えていたころの名残です。廃仏稀釈後に仁王門が随身門となり仁王と神像の安置場所がかわったわけで、神仏混淆時代の記念物です。建て方は単層入母屋造り扇垂木で俗に傘(からかさ)天井といい、天井絵の龍図は天保3(1832)雪舟の弟子磯辺等隋の作です。
序盤から息を切れますが、樹齢1000年を超える杉の御神木など坂の途中の見どころも多く、楽しみながら上ると、随身門が迎えてくれます。享保8年(1723)徳川吉宗の寄進により建立。前に左右大臣、後に仁王の守護神を配したもので太平山が寺院の山として栄えていたころの名残です。廃仏稀釈後に仁王門が随身門となり仁王と神像の安置場所がかわったわけで、神仏混淆時代の記念物です。建て方は単層入母屋造り扇垂木で俗に傘(からかさ)天井といい、天井絵の龍図は天保3(1832)雪舟の弟子磯辺等隋の作です。
 第53代淳和天皇の御代、風水害や疫病で人々が苦しむ様に心を痛まれ「下野国の霊峰三輪山に天下太平を祈る社を造営せよ」との詔を賜り、天照大御神、豊受姫大神、瓊瓊杵尊の「日・月・星」の御神徳をあらわす三座の神様をお祀りするために太平山神社が造営されました。3柱のご祭神に因み、最後の鳥居には三光神社の扁額が掲げられています。
第53代淳和天皇の御代、風水害や疫病で人々が苦しむ様に心を痛まれ「下野国の霊峰三輪山に天下太平を祈る社を造営せよ」との詔を賜り、天照大御神、豊受姫大神、瓊瓊杵尊の「日・月・星」の御神徳をあらわす三座の神様をお祀りするために太平山神社が造営されました。3柱のご祭神に因み、最後の鳥居には三光神社の扁額が掲げられています。
 本殿は江戸時代に再建され太平山の杉や檜が使われています。瓊瓊杵尊、天照大御神、豊受姫大神が祀られています。本堂前には御神石(撫で石)があり、この石を撫でることにより災厄を祓い、霊験を得るという信仰があります。
本殿は江戸時代に再建され太平山の杉や檜が使われています。瓊瓊杵尊、天照大御神、豊受姫大神が祀られています。本堂前には御神石(撫で石)があり、この石を撫でることにより災厄を祓い、霊験を得るという信仰があります。
 太平山神社ではウナギが神様を乗せて太平山に連れてきてくれたという伝承があり、そのため地元平井集落の人々はウナギは“神聖な生き物”として食べません。またウナギは「うなぎのぼり」とおいう言葉があるように“縁起の良い生き物”としても信仰され、江戸時代には徳川将軍家からうなぎをモチーフにしたご神宝が奉納されています。
太平山神社ではウナギが神様を乗せて太平山に連れてきてくれたという伝承があり、そのため地元平井集落の人々はウナギは“神聖な生き物”として食べません。またウナギは「うなぎのぼり」とおいう言葉があるように“縁起の良い生き物”としても信仰され、江戸時代には徳川将軍家からうなぎをモチーフにしたご神宝が奉納されています。
 本殿向かって右隣の「福神社」は、天之受売命・恵比須神・大国主命をお祀りしそして交通安全発祥の地と言われる「交通安全神社」がには、猿田彦命が祀られています。
本殿向かって右隣の「福神社」は、天之受売命・恵比須神・大国主命をお祀りしそして交通安全発祥の地と言われる「交通安全神社」がには、猿田彦命が祀られています。
 ほかにも「星宮神社」「蛇神神社」「足尾神社」など数多くの神社が立ち並び。“神様のデパート”と評されます。神社の社宝が星宮神社内にある火防獅子です。昔太平山が戦火に見舞われた時、獅子が守っていたご神体だけが焼け残ったことから、火事除けとして栃木市の商家に信仰されてきました。星宮神社がお寺のお堂のような造りをしているのは、江戸時代までの神仏混合の名残です。
ほかにも「星宮神社」「蛇神神社」「足尾神社」など数多くの神社が立ち並び。“神様のデパート”と評されます。神社の社宝が星宮神社内にある火防獅子です。昔太平山が戦火に見舞われた時、獅子が守っていたご神体だけが焼け残ったことから、火事除けとして栃木市の商家に信仰されてきました。星宮神社がお寺のお堂のような造りをしているのは、江戸時代までの神仏混合の名残です。
 県立自然公園にも指定されている太平山は関東平野の切れ目に位置する小高い山で、南がすべて関東平野になるためその眺望は抜群です。日本さくら名所100選に選定されています。車で上った先にあるのが謙信平駐車場で、戦国時代上杉謙信がその眺望の見事さに感嘆したことから「謙信平」と名付けられました。また渡良瀬川・古利根川」の合間に丘陵が見えることから、その眺望は明治・大正の国学者岡吉胤が“陸の松島”と讃えたほどの素晴らしさです。
県立自然公園にも指定されている太平山は関東平野の切れ目に位置する小高い山で、南がすべて関東平野になるためその眺望は抜群です。日本さくら名所100選に選定されています。車で上った先にあるのが謙信平駐車場で、戦国時代上杉謙信がその眺望の見事さに感嘆したことから「謙信平」と名付けられました。また渡良瀬川・古利根川」の合間に丘陵が見えることから、その眺望は明治・大正の国学者岡吉胤が“陸の松島”と讃えたほどの素晴らしさです。
 謙信平から眉剣坂を歩いて5分の太平山神社までの道沿いには、太平山名物の焼き鳥、玉子焼き、太平山だんごが看板メニューの茶店が並びます。昔夜鳴きするニワトリは災難を招くとして太平山に奉納する風習がある、奉納されたニワトリの卵を集めて「玉子焼き」、肉を「焼き鳥」にして功徳したのがきっかけです。また五穀豊穣を願い毎年たくさんの穀類が奉納され、奉納された米を分けて頂き粉に挽いて「太平だんご」となりました。柔らかく焼かれた玉子焼きに少し醤油を落とした大根おろしを乗せて口に入れると玉子焼きの甘さと大根おろしの苦みが口の中に広がります。目の前に広がる関東平野の風景をこの時期桜越しに見ながら食べる名物は格別です。
謙信平から眉剣坂を歩いて5分の太平山神社までの道沿いには、太平山名物の焼き鳥、玉子焼き、太平山だんごが看板メニューの茶店が並びます。昔夜鳴きするニワトリは災難を招くとして太平山に奉納する風習がある、奉納されたニワトリの卵を集めて「玉子焼き」、肉を「焼き鳥」にして功徳したのがきっかけです。また五穀豊穣を願い毎年たくさんの穀類が奉納され、奉納された米を分けて頂き粉に挽いて「太平だんご」となりました。柔らかく焼かれた玉子焼きに少し醤油を落とした大根おろしを乗せて口に入れると玉子焼きの甘さと大根おろしの苦みが口の中に広がります。目の前に広がる関東平野の風景をこの時期桜越しに見ながら食べる名物は格別です。
 北西に車を走らせ出流山へ。こちらは弘法大師御作の千手観世音菩薩をご本尊とする坂東三十三観音霊場第十七番札所 真言宗智山派 出流山満願寺とともに歩んだ山里。出流山満願寺は、さらに山奧の出流川源流部にあり、鬱蒼とした自然林や杉木立に覆われた渓間の山奥にある古刹です。仙波そばと書かれたお店の一群から一山越すと両側に出流そばのお店が立ち並び、さらに道を上がっていくと出流山満願寺の山門に到着します。鬱蒼とした杉木立の中に本堂の大御堂が立ち、静寂と荘厳な空気が訪れる者を包みます。今から1200余年前、役行者によって「観音の霊窟(奥の院鍾乳洞)」を発見されたのが始まりと伝わります。天平勝宝2年(750)日光開山の祖・勝道上人によって開山されました。
北西に車を走らせ出流山へ。こちらは弘法大師御作の千手観世音菩薩をご本尊とする坂東三十三観音霊場第十七番札所 真言宗智山派 出流山満願寺とともに歩んだ山里。出流山満願寺は、さらに山奧の出流川源流部にあり、鬱蒼とした自然林や杉木立に覆われた渓間の山奥にある古刹です。仙波そばと書かれたお店の一群から一山越すと両側に出流そばのお店が立ち並び、さらに道を上がっていくと出流山満願寺の山門に到着します。鬱蒼とした杉木立の中に本堂の大御堂が立ち、静寂と荘厳な空気が訪れる者を包みます。今から1200余年前、役行者によって「観音の霊窟(奥の院鍾乳洞)」を発見されたのが始まりと伝わります。天平勝宝2年(750)日光開山の祖・勝道上人によって開山されました。
下野国司(介)の若田高藤の妻がこの「観音の霊窟」で子宝を得ることができるということを聞いて、21日間ここに籠り、翌天平7年に男の子を授かりました。この子が後の日光開山の祖・勝道上人です。以来当山の奥の院にお祀りされている鍾乳洞で自然にできた「十一面観音菩薩」は子授け、安産、子育てのご利益があると信仰されています。
中世には足利氏の庇護となり修験道の拠点として寺運が隆盛すると出羽三山詣での行者は、出流山満願寺にも詣でないと三山全て登拝したとしても大願成就しないとの教えが信じられ、寺号の「満願寺」もこの信仰に由来するとされています。また勝道上人が日光山を開いた人物であったことから江戸幕府に庇護され、日光山の修行僧は一度は出流山で修行しなければなりませんでした。
山門である仁王門は徳川時代の享保20年(1735)の建立。三間一戸、桁行3間、梁間2間、八脚楼門で入母屋、銅板瓦棒葺き、外壁は真壁造り板張り、上層目には高欄、「出流山」の山号額、左右には目象窓があります。下層目の両側にある一対の朱色の仁王尊像は足利時代の作。以前は茅葺き屋根でしたが昭和初期に金属板に葺き替えています。
 山門をくぐってすぐの薬師堂は享保年間(1716~1736)の建立で薬師如来を安置しています。木造平屋建て、宝形造、銅板瓦棒葺き、桁行3間、梁間3間、正面1間拝付き、外壁は真壁造り白漆喰仕上げ、木部朱塗りです。江戸時代の満願寺には本坊に加えて六つの塔頭寺院(福性院・清光院・多聞院・延命院・宝光院・月輪院)と二つの修験行者坊(常福院・胎蔵院)がありますたが、薬師堂はその一つ福性院の名残をとどめる建物です。
山門をくぐってすぐの薬師堂は享保年間(1716~1736)の建立で薬師如来を安置しています。木造平屋建て、宝形造、銅板瓦棒葺き、桁行3間、梁間3間、正面1間拝付き、外壁は真壁造り白漆喰仕上げ、木部朱塗りです。江戸時代の満願寺には本坊に加えて六つの塔頭寺院(福性院・清光院・多聞院・延命院・宝光院・月輪院)と二つの修験行者坊(常福院・胎蔵院)がありますたが、薬師堂はその一つ福性院の名残をとどめる建物です。
 鐘楼は明治4年(1871)に失ってから約100年ぶりの昭和59年(1984)にほぼ同じ場所に再建されています。
鐘楼は明治4年(1871)に失ってから約100年ぶりの昭和59年(1984)にほぼ同じ場所に再建されています。
 杉木立の中に立つ本堂(大御堂)は、後小松天皇の応安元年(1368)、足利義光公の寄進によって観音堂として建立されましたが、元文5年(1740)12月20日の大火で山門を残して焼失。現在の大御堂は、明和元年(1764)8月に中興第17世道呆和尚によって営々辛苦の末に再建されたもので、徳川中期の堂宇建築の代表的なものと言われます。
杉木立の中に立つ本堂(大御堂)は、後小松天皇の応安元年(1368)、足利義光公の寄進によって観音堂として建立されましたが、元文5年(1740)12月20日の大火で山門を残して焼失。現在の大御堂は、明和元年(1764)8月に中興第17世道呆和尚によって営々辛苦の末に再建されたもので、徳川中期の堂宇建築の代表的なものと言われます。
 八間四面入母屋造り、銅板葺き、外壁は真壁造り板張り、正面に3間の唐破風向拝が付いています。三手先に竜の彫刻が施され、建物全体が朱色で着色され、精巧な彫刻には極彩色で彩られています。筑波山の大御堂、奈良の興福寺大御堂とともに日本三御堂のひとつと称されています。特に本堂の軒を支える三手先には見事な龍の彫刻がなされています。
八間四面入母屋造り、銅板葺き、外壁は真壁造り板張り、正面に3間の唐破風向拝が付いています。三手先に竜の彫刻が施され、建物全体が朱色で着色され、精巧な彫刻には極彩色で彩られています。筑波山の大御堂、奈良の興福寺大御堂とともに日本三御堂のひとつと称されています。特に本堂の軒を支える三手先には見事な龍の彫刻がなされています。
 内部は内外陣に分れ、内陣に須弥壇を設け、弘仁11年(820)、勝道上人の徳を慕って参詣した弘法大師が当山の銘木で造立された千手観世音菩薩がご本尊として安置されています。また左に勝道上人、右に弘法大師を祀っています。
内部は内外陣に分れ、内陣に須弥壇を設け、弘仁11年(820)、勝道上人の徳を慕って参詣した弘法大師が当山の銘木で造立された千手観世音菩薩がご本尊として安置されています。また左に勝道上人、右に弘法大師を祀っています。
 本堂から1kmほどの山道を歩いた先に奥之院があります。写真は御沢の清流に沿って続く奥之院への入口です。
本堂から1kmほどの山道を歩いた先に奥之院があります。写真は御沢の清流に沿って続く奥之院への入口です。
 途中には、如漣堂や聖天堂、女人堂があり往時の隆盛を物語っています。明治の頃、日本鉄道・日光線(現JR東日本・日光線)開通後に衰退した満願寺を、成田山のお不動さまのお告げでやってきた松丸女漣尼という人が出流山の霊験あらたかなことを伝えたことが大きく、復興に尽力したとのこと。弘法大師をご本尊とする女人堂は、奥之院の参道沿い「大師の霊窟」の真下にあります。昔はここから「大師の霊廟」に入れない女性の信者は、ここで同行の男性信者の帰りを待っていたそうです。「大師の霊窟」は弘法大師が当山を訪れた際に禅定したとされる霊窟です。
途中には、如漣堂や聖天堂、女人堂があり往時の隆盛を物語っています。明治の頃、日本鉄道・日光線(現JR東日本・日光線)開通後に衰退した満願寺を、成田山のお不動さまのお告げでやってきた松丸女漣尼という人が出流山の霊験あらたかなことを伝えたことが大きく、復興に尽力したとのこと。弘法大師をご本尊とする女人堂は、奥之院の参道沿い「大師の霊窟」の真下にあります。昔はここから「大師の霊廟」に入れない女性の信者は、ここで同行の男性信者の帰りを待っていたそうです。「大師の霊窟」は弘法大師が当山を訪れた際に禅定したとされる霊窟です。
 並んだ五輪塔は、歴代の御住職の墓石です。
並んだ五輪塔は、歴代の御住職の墓石です。
 参拝道の行き止まりには、出流川の源泉である「胎内くぐり」の鍾乳洞の湧き水が直接流れ落ちる落差8mの大悲の滝があります。滝行が行われる場所で岩場の上から不動明王などの3体の仏像が見守っています。ここで滝行をすれば、観世音菩薩の大慈悲に浴するということから「大悲の滝」と呼ばれています。大悲の滝から荒れた参道をさらに上がると「大日の霊窟」があり、釈迦如来、勢至菩薩等に見立てた鍾乳石があるそうです。
参拝道の行き止まりには、出流川の源泉である「胎内くぐり」の鍾乳洞の湧き水が直接流れ落ちる落差8mの大悲の滝があります。滝行が行われる場所で岩場の上から不動明王などの3体の仏像が見守っています。ここで滝行をすれば、観世音菩薩の大慈悲に浴するということから「大悲の滝」と呼ばれています。大悲の滝から荒れた参道をさらに上がると「大日の霊窟」があり、釈迦如来、勢至菩薩等に見立てた鍾乳石があるそうです。
 ここから左方を見上げると崖の中腹、岩壁に張り付くように立つ奥之院が現れます。山道を歩いた者しか辿り着けないパワースポットです。
ここから左方を見上げると崖の中腹、岩壁に張り付くように立つ奥之院が現れます。山道を歩いた者しか辿り着けないパワースポットです。
 大悲の滝から急な石段を100余段上ると「観音の霊窟」の拝殿に昇殿します。高さ4m余りのこの拝殿が鍾乳洞の入口になっています。拝殿奥には三面六臂の大黒天、十一面観世音菩薩、勝道上人の像が置かれています。
大悲の滝から急な石段を100余段上ると「観音の霊窟」の拝殿に昇殿します。高さ4m余りのこの拝殿が鍾乳洞の入口になっています。拝殿奥には三面六臂の大黒天、十一面観世音菩薩、勝道上人の像が置かれています。
 そして右手奥が鍾乳洞「大悲霊窟」でその中に中にあるのが「十一面観世菩薩音の後ろ姿の像」という、天然の鍾乳石でできた尊像を拝みます。左右には八面六臂の大黒天の後ろ姿と勝道上人の後ろ姿があり、台座となる伏せ蓮華を含めると高さ4mと大きな鍾乳石です。
そして右手奥が鍾乳洞「大悲霊窟」でその中に中にあるのが「十一面観世菩薩音の後ろ姿の像」という、天然の鍾乳石でできた尊像を拝みます。左右には八面六臂の大黒天の後ろ姿と勝道上人の後ろ姿があり、台座となる伏せ蓮華を含めると高さ4mと大きな鍾乳石です。
 出流山には奥之院「観音の霊窟」のほかにも「大日の霊窟」「大師の霊窟」「不動尊霊窟」「普賢の霊窟」等の霊窟があるとのことで山全体が石灰石であることから仏様に見立てた鍾乳石があるそうです。
出流山には奥之院「観音の霊窟」のほかにも「大日の霊窟」「大師の霊窟」「不動尊霊窟」「普賢の霊窟」等の霊窟があるとのことで山全体が石灰石であることから仏様に見立てた鍾乳石があるそうです。
麓の老舗そば店「いづるや」で大ざるに盛られた名物そばを味わえば、栃木市郊外の太平山と出流山は、人々の祈りに根ざした観光地であることを改めて感じます。二つの寺社を訪ねたあとは、栃木の蔵の街にも立ち寄りたいものです。 「遊覧船で麗らかな時間も!蔵の町栃木の日光例幣使街道を歩く」はこちらhttps://wakuwakutrip.com/archives/10634