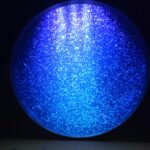今から約1200年前の平安時代初め、南都(奈良)で法相宗を学んだ僧・徳一は、霊峰磐梯山を望む山麓に修行の拠点として慧日寺を開創。寺は繁栄し、会津仏教文化の礎が築かれました。しかしながら、武家社会の伸展と共に寺勢は衰退を始め、中世から近世にかけ戦乱や火災が重なり建物や仏像は焼失・散逸してしまいました。明治2年(1869)の廃寺から100年を経た昭和45年(1970)には、広大な寺跡が国の史跡に指定され、発掘調査の成果をもとに平成20年(2008)には金堂・中門が復元されました。1200年の時を越えて会津仏教文化発祥の地に甦った古代儀礼空間の雰囲気を味わいます。
奈良、京都、鎌倉、平泉と並ぶ、いわゆる“五大仏都”の一つとされる会津。日本遺産「会津三十三観音めぐり~巡礼を通して観た往時の会津文化~」として選出されています。仏教がこの地に伝わったのは6世紀中頃という伝承もありますが、“仏都”となる礎を築いたとされるのは、平安時代初期に日本の仏教界で活躍した高僧・徳一です。きっかけは会津磐梯山の噴火だったといいます。平安時代初期に大噴火し、麓の人たちは自然の力に怯え、救いを求めました。そこに奈良の興福寺などで学んだ僧・徳一が現れ、災害に苦しむ人たちの心のよりどころとして仏教を広めることになります。
徳一の出自は不明で生没年も不詳で諸説ありますが、一般的には天応元年(781)に生まれ、承和9年(842)62歳で亡くなったという説が有力とされています。幼いころに平城京で、釈迦の正統を標榜する法相宗を中心に、南都六宗と呼ばれた奈良仏教の各派を興福寺で学びます。延暦13年(794)桓武天皇は奈良から京都へ遷都して奈良仏教の腐敗を一掃しました。徳一も軌を一にして堕落した奈良の仏教界を去り、都と離れた閑静な地で修行を積むことを東国に求め、国分寺も国分尼寺もない会津の地に、延暦20年(801)頃移り住んだといいます。写真は復元された中門
 法相宗の教えと薬師信仰を携えた徳一は、当時の仏教僧たちが山林修行に大きな価値を置いていたように、会津に入った後、畏怖されながらも山岳信仰の地であった磐梯山で修行に励み、人々に仏教を広めました。磐梯山を「宝の山」として崇める一方、災害ばかりでなく「病魔の山」と畏れられる民衆を、病気平癒の仏でありながら同時に怨霊を鎮め猛獣や自然災害から人々を救い衣食財宝の福徳をもたらす現世利益の仏でもある薬師如来信仰で力強く導いたのです。写真は復元された金堂
法相宗の教えと薬師信仰を携えた徳一は、当時の仏教僧たちが山林修行に大きな価値を置いていたように、会津に入った後、畏怖されながらも山岳信仰の地であった磐梯山で修行に励み、人々に仏教を広めました。磐梯山を「宝の山」として崇める一方、災害ばかりでなく「病魔の山」と畏れられる民衆を、病気平癒の仏でありながら同時に怨霊を鎮め猛獣や自然災害から人々を救い衣食財宝の福徳をもたらす現世利益の仏でもある薬師如来信仰で力強く導いたのです。写真は復元された金堂
 大同2年(807)にはその拠点として磐梯山麓に慧日寺を建立し、関東北部から東北南部で教化活動を展開し、仏都会津はここに始まります。最盛期は東国屈指の大寺院として広く名を馳せたと言われ、寺僧三百、僧兵数千、寺領18万石、子院3800と寺勢を誇り、会津には圓蔵寺、勝常寺、法用寺、如法寺、鳥追観音など、徳一ゆかりの寺が今も数多く残されています。創建当初の本尊は薬師如来で、長い歴史の中で度々の火災などにより失われましたが、復元金堂内に再現されました。
大同2年(807)にはその拠点として磐梯山麓に慧日寺を建立し、関東北部から東北南部で教化活動を展開し、仏都会津はここに始まります。最盛期は東国屈指の大寺院として広く名を馳せたと言われ、寺僧三百、僧兵数千、寺領18万石、子院3800と寺勢を誇り、会津には圓蔵寺、勝常寺、法用寺、如法寺、鳥追観音など、徳一ゆかりの寺が今も数多く残されています。創建当初の本尊は薬師如来で、長い歴史の中で度々の火災などにより失われましたが、復元金堂内に再現されました。
 天台宗(805年)、真言宗(806年)の創始と同時期であり、空海は、徳一の厳しい修行態度と教化の旅を賞賛し、「徳一菩薩」とまで尊称している。これに対して徳一は真言宗の祖・空海に対し、真言宗に対する疑問を11項目にまとめた『真言宗未決文』を提示しています。また天台宗の祖・最澄に対しては、一乗が釈尊の真意を示すものではないと天台宗の教えを批判し、一乗こそ真実であるとして厳しく応酬した最澄と『三一権実論争』と呼ばれる批判を繰り広げ、日本仏教の深化に寄与したことでも知られます。
天台宗(805年)、真言宗(806年)の創始と同時期であり、空海は、徳一の厳しい修行態度と教化の旅を賞賛し、「徳一菩薩」とまで尊称している。これに対して徳一は真言宗の祖・空海に対し、真言宗に対する疑問を11項目にまとめた『真言宗未決文』を提示しています。また天台宗の祖・最澄に対しては、一乗が釈尊の真意を示すものではないと天台宗の教えを批判し、一乗こそ真実であるとして厳しく応酬した最澄と『三一権実論争』と呼ばれる批判を繰り広げ、日本仏教の深化に寄与したことでも知られます。
慧日寺は総面積16万㎡に及ぶ広大な地域が貴重な文化遺産として保存されています。初期の中心伽藍は中門-金堂-講堂-食堂が南北に建ち並んでいたことが判明していて、史跡整備では、講堂・食堂は平面表示に、中門・金堂は立体復元されました。金堂は平安初期の古式建築技法により復元されています。
 慧日寺の隆盛も源平の戦あたりから翳りを見せます。『平家物語』には慧日寺の宗徒頭だった乗丹坊という僧が、会津四郡の兵士を率いてを信濃国に出兵し、横田原合戦で木曽義仲と決戦して敗れたくだりがあり、平家方に組みしたことから衰えが始まり、室町時代の火災と伊達政宗の会津侵攻によって破壊されて衰退へと。ついには明治時代の廃仏毀釈により寺は廃されます。寺域にある苔むした乗丹坊の供養塔や「乗丹坊の木ざしザクラ」でその名を知ることができます。今から800年以上前、慧日寺の宗徒頭であった乗丹坊が挿した桜の杖がこの樹になったとの伝承を持つエドヒガンザクラの古木です。かつてはこの桜が花咲くのを待って種籾を播く風習があったことから、農事暦の基準木として「種播きザクラ」と呼ばれています。春には薄紅色から白色の可憐で小さな花を付け、粉雪を掃いたように舞い散る散り際は、山里を彩る春の風物詩にもなっています。ヤマザクラと共に、桜の中では非常に長寿の種として知られており、幹周り約5m、樹高約15mを誇る名木です。
慧日寺の隆盛も源平の戦あたりから翳りを見せます。『平家物語』には慧日寺の宗徒頭だった乗丹坊という僧が、会津四郡の兵士を率いてを信濃国に出兵し、横田原合戦で木曽義仲と決戦して敗れたくだりがあり、平家方に組みしたことから衰えが始まり、室町時代の火災と伊達政宗の会津侵攻によって破壊されて衰退へと。ついには明治時代の廃仏毀釈により寺は廃されます。寺域にある苔むした乗丹坊の供養塔や「乗丹坊の木ざしザクラ」でその名を知ることができます。今から800年以上前、慧日寺の宗徒頭であった乗丹坊が挿した桜の杖がこの樹になったとの伝承を持つエドヒガンザクラの古木です。かつてはこの桜が花咲くのを待って種籾を播く風習があったことから、農事暦の基準木として「種播きザクラ」と呼ばれています。春には薄紅色から白色の可憐で小さな花を付け、粉雪を掃いたように舞い散る散り際は、山里を彩る春の風物詩にもなっています。ヤマザクラと共に、桜の中では非常に長寿の種として知られており、幹周り約5m、樹高約15mを誇る名木です。
 寺域の最奥にある「徳一廟」には、徳一菩薩の墓とも伝わる平安末期の様式がみられる五重石層塔が安置され、供養塔と思われます。長く三層の状態でしたが、発掘調査の結果、屋根石が見つかり、本来は5層に石塔であったことが分かりました。安山岩製で、初重のみ軸部を別石で造り、そのほかは屋根石の上に上層の軸部を造り出して重ねています。屋根石の表面には錣葺を表現した段加工がみられ、さらに軒先の四隅には風鐸をつり下げたと思われる孔が残っています。昭和20年頃大雪で石塔が倒壊した際に軸部の納入孔から9世紀代の土師器の甕が発見されたことから、徳一の寂年代からさほど隔たりのない頃の造立と推定されています。かつて、周辺の住民が石塔を削り、薬として服用したという風習は、慧日寺の本尊であった薬師如来の信仰によるものと思われます。現在覆堂を建設し保存が図られています。
寺域の最奥にある「徳一廟」には、徳一菩薩の墓とも伝わる平安末期の様式がみられる五重石層塔が安置され、供養塔と思われます。長く三層の状態でしたが、発掘調査の結果、屋根石が見つかり、本来は5層に石塔であったことが分かりました。安山岩製で、初重のみ軸部を別石で造り、そのほかは屋根石の上に上層の軸部を造り出して重ねています。屋根石の表面には錣葺を表現した段加工がみられ、さらに軒先の四隅には風鐸をつり下げたと思われる孔が残っています。昭和20年頃大雪で石塔が倒壊した際に軸部の納入孔から9世紀代の土師器の甕が発見されたことから、徳一の寂年代からさほど隔たりのない頃の造立と推定されています。かつて、周辺の住民が石塔を削り、薬として服用したという風習は、慧日寺の本尊であった薬師如来の信仰によるものと思われます。現在覆堂を建設し保存が図られています。
 また中心伽藍整備地区からは少し外れますが、南に仁王門があります。現在の仁王門は江戸時代後期頃に建立されたもので、平面規模が大きく、木柄が太い独特の特徴を有し、近世の慧日寺の伽藍を伝える重要な建造物です。
また中心伽藍整備地区からは少し外れますが、南に仁王門があります。現在の仁王門は江戸時代後期頃に建立されたもので、平面規模が大きく、木柄が太い独特の特徴を有し、近世の慧日寺の伽藍を伝える重要な建造物です。
 さらに仁王門をくぐると薬師堂が建っています。会津には多くの薬師堂がありますが、慧日寺は現在でも会津五薬師のひとつ、東方薬師として親しまれています。慧日寺の本尊であった薬師如来像は、平安時代初期は金堂に祀られ、慧日寺繁栄の中で篤い信仰を集めていました。しかし伽藍は長い間に度々の火災や戦災により変遷し、近世には寛永15年(1638)薬師如来像も薬師堂に祀られるようになりました。こも薬師堂も明治5年(1872)には付近の火災の延焼により、薬師如来像とともに焼失してしまいました。しかし現在の薬師堂は明治22年に再建されたもので桁行・梁間とも三間の寄棟造りです。
さらに仁王門をくぐると薬師堂が建っています。会津には多くの薬師堂がありますが、慧日寺は現在でも会津五薬師のひとつ、東方薬師として親しまれています。慧日寺の本尊であった薬師如来像は、平安時代初期は金堂に祀られ、慧日寺繁栄の中で篤い信仰を集めていました。しかし伽藍は長い間に度々の火災や戦災により変遷し、近世には寛永15年(1638)薬師如来像も薬師堂に祀られるようになりました。こも薬師堂も明治5年(1872)には付近の火災の延焼により、薬師如来像とともに焼失してしまいました。しかし現在の薬師堂は明治22年に再建されたもので桁行・梁間とも三間の寄棟造りです。
 発掘調査によって1200年の歴史が甦る慧日寺で古代儀礼空間の雰囲気を体感するならイベントの開催の合わせて訪ねてみましょう。5月には「月待ちの灯り」が開催されライトアップされます。日本夜景遺産に認定。
発掘調査によって1200年の歴史が甦る慧日寺で古代儀礼空間の雰囲気を体感するならイベントの開催の合わせて訪ねてみましょう。5月には「月待ちの灯り」が開催されライトアップされます。日本夜景遺産に認定。