城跡のお城周りを中心に、歴史的な建物がいまだに残る篠山。篠山城址周辺は豊かな自然を感じながら、歴史に触れたり、お買い物をしたり、町歩きの魅力がたっぷりです。商店がならぶ二階町、町家の趣ある佇まいの店が並ぶ河原町を中心に、老舗はもちろん、カフェやスイーツ店など町家造りをそのまま生かした、新しいお店も増え続けています。昔と今が同居する、丹波篠山の町並みを散策するのは楽しいものですよ。
なんと言っても瀬戸内海から日本海まであって山もある県は兵庫県だけであろう。その中でも大注目は丹波篠山です。多紀連山をはじめとする山々に囲まれた篠山盆地の中心にある多兵庫県多紀郡には、篠山市誕生以前は、篠山町・今田町・丹南町・西紀町の4町があり、近世篠山藩の支配を受けていました。特に篠山町は、篠山藩の城下町として、近世以来、多紀郡の中心として発展してきたこともあり、この篠山町を中心とした多紀郡4町は比較的まとまりをもった地域です。。
「篠山」の地名は篠山城が築かれた「笹山」が由来といい、篠山盆地の中央に位置する湿地帯に囲まれた独立丘陵で、周囲に笹が繁っていた上、信仰の対象とされる聖々山でした。慶長13年(1608)徳川家康は豊臣氏の居城である大阪城と山陰、山陽路の連絡を断ち、西国大名に対する抑えとするため、常陸国の笠間城から実子松平康重を八上城に移し、ただちに新城の築城を命じたのです。慶長14年(1609)、姫路城主池田輝政が普請総奉行として指揮を執り、縄張は築城名人として名高い藤堂高虎が担当。浅野幸長、加藤嘉明、福島正則など丹波国より西の15カ国・20の諸大名に夫役を命じた天下普請で行われ、一日約8万人を動員してわずか6ヶ月で「笹山」という丘陵に城を完成させ、それを中心に拡がった城下町が篠山です。初代城主として松平康重が八上城から移り、松平三家8代と青山6代といずれも徳川譜代の有力大名に引継がれ、260年余の幕藩体制 のもと篠山藩5万石の政治・経済・文化の拠点としてその役割を果たしてきました。
お城の北側の二階町、東側には古民家が建ち並ぶ河原町妻入商家群、西側の御徒士町武家屋敷群など、城下町篠山は、篠山城を中心に古来京都への交通の要として栄えてきた歴史があり、町並みや祭りなどに京文化の影響を受けながら、丹波の都として栄え発展してきました。そのため兵庫県でも旧丹波国に当たるため神戸より京都との方が結びつきが強く、京文化を色濃く残しています。そんな城下町篠山の街並みは「美しい日本の歴史的風土100選」に選ばれています。
 JR尼崎乗換えで丹波路快速でJR篠山口まで1時間半。JR篠山口駅から農免道路4kmほど歩くと加古川源流にあたる篠山川に出ます。この川を渡る渡良瀬橋の欄干には篠山名物のぼたん鍋からの連想なのかイノシシのオブジェが置かれています。その篠山川に藤岡川が合流するあたりからは兵庫県の「ふるさと桜づつみ回廊」の最初に整備された場所で、春には桜のピンクと清流の青との共演が楽しめます。
JR尼崎乗換えで丹波路快速でJR篠山口まで1時間半。JR篠山口駅から農免道路4kmほど歩くと加古川源流にあたる篠山川に出ます。この川を渡る渡良瀬橋の欄干には篠山名物のぼたん鍋からの連想なのかイノシシのオブジェが置かれています。その篠山川に藤岡川が合流するあたりからは兵庫県の「ふるさと桜づつみ回廊」の最初に整備された場所で、春には桜のピンクと清流の青との共演が楽しめます。
 篠山城址へ向かう篠山城跡北外濠一帯は鳳鳴義塾(現兵庫県立篠山鳳鳴高等学校)跡で、このあたりは官公庁関係の建物が多く、なかでも大正ロマン館の建物は、大正12年(1923)4月の落成当時、篠山の町では最もモダンな建物で、明治、大正の代表的な洋風建築として価値があります。実際大正12年から平成4年まで篠山町役場で現在は観光の中核施設として活用されています。
篠山城址へ向かう篠山城跡北外濠一帯は鳳鳴義塾(現兵庫県立篠山鳳鳴高等学校)跡で、このあたりは官公庁関係の建物が多く、なかでも大正ロマン館の建物は、大正12年(1923)4月の落成当時、篠山の町では最もモダンな建物で、明治、大正の代表的な洋風建築として価値があります。実際大正12年から平成4年まで篠山町役場で現在は観光の中核施設として活用されています。
 北外堀を渡り、三の丸広場(現駐車場)まで来れば、2006年日本100名城に選定された「篠山城跡」に到着です。武家町や商家町の佇まいが残る城下町・篠山の要である篠山城は、回字型の構造から輪郭式縄張という城郭遺構で、掘や石垣、馬出などの遺構がほぼ昔のままの姿をとどめています。
北外堀を渡り、三の丸広場(現駐車場)まで来れば、2006年日本100名城に選定された「篠山城跡」に到着です。武家町や商家町の佇まいが残る城下町・篠山の要である篠山城は、回字型の構造から輪郭式縄張という城郭遺構で、掘や石垣、馬出などの遺構がほぼ昔のままの姿をとどめています。
 別名桐ヶ城と呼ぶこの城は、築城家の第一人者、藤堂高虎の縄張りで行われた平山城で防御性を叶えた無駄のない設計。方形約400mの小規模なものであるものの、本丸と二の丸を内堀で囲み、外側を三の丸、その外側を外濠で囲む。本丸と二の丸は高い石垣で囲まれた上に多聞櫓が鉄壁のように立ちはだかり、二の丸には大小書院や御殿、築山を持つ庭園を配し、要所には2重の枡形虎口や2重、3重の櫓を配した荘厳かつ堅固なものです。外濠の幅は約45mと広く、なかなか近づけない工夫がかんじられます。石垣の下部に設けられた犬走も藤堂高虎が好んで築いたもので建物や堀との間の細長い空き地は、もろい地盤を補強する意味もあり、今治城と共通する。
別名桐ヶ城と呼ぶこの城は、築城家の第一人者、藤堂高虎の縄張りで行われた平山城で防御性を叶えた無駄のない設計。方形約400mの小規模なものであるものの、本丸と二の丸を内堀で囲み、外側を三の丸、その外側を外濠で囲む。本丸と二の丸は高い石垣で囲まれた上に多聞櫓が鉄壁のように立ちはだかり、二の丸には大小書院や御殿、築山を持つ庭園を配し、要所には2重の枡形虎口や2重、3重の櫓を配した荘厳かつ堅固なものです。外濠の幅は約45mと広く、なかなか近づけない工夫がかんじられます。石垣の下部に設けられた犬走も藤堂高虎が好んで築いたもので建物や堀との間の細長い空き地は、もろい地盤を補強する意味もあり、今治城と共通する。
 大手門から南東を見た篠山城の本丸と二の丸を囲む内堀は、廃城後に埋め立てられ往時の姿を留めていませんでした。そのため内堀石垣全体の復元整備が行われています。江戸時代の古絵図によると、この場所には内堀石垣と一体となった櫓台がありました。櫓台とは敵の侵入を防ぐために設けられた防御施設の一種です。
大手門から南東を見た篠山城の本丸と二の丸を囲む内堀は、廃城後に埋め立てられ往時の姿を留めていませんでした。そのため内堀石垣全体の復元整備が行われています。江戸時代の古絵図によると、この場所には内堀石垣と一体となった櫓台がありました。櫓台とは敵の侵入を防ぐために設けられた防御施設の一種です。
 大手門と鉄門との間にある侵入した敵軍の動きを妨げるための方形の広場である枡形を有し、石垣は滋賀近江の穴太衆によるもの。自然石をあまり加工しないで積む「野面積み」と、出角は「算木積み」の工法を用いています。
大手門と鉄門との間にある侵入した敵軍の動きを妨げるための方形の広場である枡形を有し、石垣は滋賀近江の穴太衆によるもの。自然石をあまり加工しないで積む「野面積み」と、出角は「算木積み」の工法を用いています。
 枡形を抜けると鉄門の正面に篠山城のハイライトである、2000年に復元された京都二条城の御殿に匹敵する大書院が現れます。
枡形を抜けると鉄門の正面に篠山城のハイライトである、2000年に復元された京都二条城の御殿に匹敵する大書院が現れます。
 大書院は、二の丸跡に所在した城主居館の中で、とくに歴代藩主による公式行事に使用された場所で、正規の書院造の建物となっていました。この建物は慶長4年(1609)の築城時、木造住宅建築としては非常に大きく、大きさは東西28m、南北26mの篠山城最大の規模となっていました。京都二条城の御殿を参考にして建てられと伝えられるように、現存する同様の建築の中では京都二条城二の丸御殿の遠侍と呼ばれる建物と部屋割りや外観がよく似ています。二条城の御殿は将軍が上洛した時の宿所になった第一級の建物ということから、大書院は一大名の書院としては破格の規模と古式の建築様式を備えたものと言えます。慶長14年(1609)の篠山城築城とほぼ同時に建てられ、約260年間にわたって藩の公式行事などに使用されました。明治維新による廃城令後も残されましたが、残念ながら昭和19年(1944)1月に焼失。その後平成12年(2000)に復元再建されました。写真は南側から見た大書院と二ノ丸御殿跡
大書院は、二の丸跡に所在した城主居館の中で、とくに歴代藩主による公式行事に使用された場所で、正規の書院造の建物となっていました。この建物は慶長4年(1609)の築城時、木造住宅建築としては非常に大きく、大きさは東西28m、南北26mの篠山城最大の規模となっていました。京都二条城の御殿を参考にして建てられと伝えられるように、現存する同様の建築の中では京都二条城二の丸御殿の遠侍と呼ばれる建物と部屋割りや外観がよく似ています。二条城の御殿は将軍が上洛した時の宿所になった第一級の建物ということから、大書院は一大名の書院としては破格の規模と古式の建築様式を備えたものと言えます。慶長14年(1609)の篠山城築城とほぼ同時に建てられ、約260年間にわたって藩の公式行事などに使用されました。明治維新による廃城令後も残されましたが、残念ながら昭和19年(1944)1月に焼失。その後平成12年(2000)に復元再建されました。写真は南側から見た大書院と二ノ丸御殿跡
 大書院を復元するにあたっては、古絵図、古写真、発掘などの総合的な学術調査が実施され、その成果に基づいて設計と建築が行われました。復元された建物は平屋建てで北(妻側)を建物正面とし、床面積は739.33㎡、棟高は12.88mあり、屋根は入母屋造・杮葺となっています。東北隅には中門があり、正面(北)には車寄、そしてその屋根には軒唐破風がついています。総工費約12億円
大書院を復元するにあたっては、古絵図、古写真、発掘などの総合的な学術調査が実施され、その成果に基づいて設計と建築が行われました。復元された建物は平屋建てで北(妻側)を建物正面とし、床面積は739.33㎡、棟高は12.88mあり、屋根は入母屋造・杮葺となっています。東北隅には中門があり、正面(北)には車寄、そしてその屋根には軒唐破風がついています。総工費約12億円
 大書院内部には襖絵などに囲まれた上段の間や孔雀の間など8つの部屋があり、その周囲に広縁が、さらにその外側には落縁が一段低く設けられています。
大書院内部には襖絵などに囲まれた上段の間や孔雀の間など8つの部屋があり、その周囲に広縁が、さらにその外側には落縁が一段低く設けられています。
 上段の間は大書院の中で最も格式の高い部屋であり、幅3.5間(6.9m)の大床、その左手に付書院、右手には天袋、違棚、帳台構が設けられた正規の書院造りになっています。こういった座敷を飾るしつらえが整うのは、大書院が創建された慶長頃のことと考えられています。この上段の間には往時の雰囲気を再現させるため、江戸時代初期の狩野派の絵師が描いた屏風絵を床貼り付けや襖等に障壁画として転用されています。上段の間の大床は「老松図」、天袋は「花卉図」、違棚は「松竹梅雉子図」、帳台構は「牡丹図」、次の間襖四面は「籬に菊図」を用い、華やいだ中にも移りゆく季節感をかもしだすようになっています。
上段の間は大書院の中で最も格式の高い部屋であり、幅3.5間(6.9m)の大床、その左手に付書院、右手には天袋、違棚、帳台構が設けられた正規の書院造りになっています。こういった座敷を飾るしつらえが整うのは、大書院が創建された慶長頃のことと考えられています。この上段の間には往時の雰囲気を再現させるため、江戸時代初期の狩野派の絵師が描いた屏風絵を床貼り付けや襖等に障壁画として転用されています。上段の間の大床は「老松図」、天袋は「花卉図」、違棚は「松竹梅雉子図」、帳台構は「牡丹図」、次の間襖四面は「籬に菊図」を用い、華やいだ中にも移りゆく季節感をかもしだすようになっています。
 二の丸は、大書院、小書院、中奥御殿、奥御殿、台所などの建物と築山をもつ庭園があり、儀式、執務を行う場と城主の生活空間の場で篠山城で最も重要な場所でした。これら御殿群の周囲には三層の櫓1棟、二層の隅櫓5棟とそれをつなぐように多聞櫓と門が配置されていました。
二の丸は、大書院、小書院、中奥御殿、奥御殿、台所などの建物と築山をもつ庭園があり、儀式、執務を行う場と城主の生活空間の場で篠山城で最も重要な場所でした。これら御殿群の周囲には三層の櫓1棟、二層の隅櫓5棟とそれをつなぐように多聞櫓と門が配置されていました。
 二の丸御殿跡の平面復元は江戸時代中期頃の古絵図をもとに平成14年(2002)に完成。主に藩主の生活の場だったところで、御休息の間や御用人詰所、台所、厠など各室を御影石で区切り、部屋名を表示しています。写真は往時の名残をとどめる二の丸御殿庭園の井戸
二の丸御殿跡の平面復元は江戸時代中期頃の古絵図をもとに平成14年(2002)に完成。主に藩主の生活の場だったところで、御休息の間や御用人詰所、台所、厠など各室を御影石で区切り、部屋名を表示しています。写真は往時の名残をとどめる二の丸御殿庭園の井戸
 南面中央の少し低い位置にある埋門は、字のごとく石垣に埋まるように造られていて、扉は小さな木戸になっています。非常時には土や石で埋めて遮断することができる特殊な造りになっています。
南面中央の少し低い位置にある埋門は、字のごとく石垣に埋まるように造られていて、扉は小さな木戸になっています。非常時には土や石で埋めて遮断することができる特殊な造りになっています。
 またこの門を出た南角には普請総奉行を務めた姫路城主・池田三左衛門輝政のものといわれる三左衛門の刻印が刻まれた石垣が発見できます。
またこの門を出た南角には普請総奉行を務めた姫路城主・池田三左衛門輝政のものといわれる三左衛門の刻印が刻まれた石垣が発見できます。
 二の丸の東には篠山城の最後の砦となる本丸跡があります。築城当初は現在の二の丸が本丸、現在の本丸は南東の隅に、天守台が造られたことから、特に殿守丸と呼ばれていました。本丸の周囲は天守台と南西隅・北西隅・北東隅の三カ所に二重の隅櫓を建て、間を多聞櫓でつないで内部を囲んでいました。二の丸には大書院をはじめとする御殿が建てられたのに対して、本丸には御殿等の建物は無かったようです。本丸内の北側中央にある一の井戸は岩盤を堀り抜いたもので、深さ約16m(水深約8m)で、掘るのに2年もかかったと伝えれています。
二の丸の東には篠山城の最後の砦となる本丸跡があります。築城当初は現在の二の丸が本丸、現在の本丸は南東の隅に、天守台が造られたことから、特に殿守丸と呼ばれていました。本丸の周囲は天守台と南西隅・北西隅・北東隅の三カ所に二重の隅櫓を建て、間を多聞櫓でつないで内部を囲んでいました。二の丸には大書院をはじめとする御殿が建てられたのに対して、本丸には御殿等の建物は無かったようです。本丸内の北側中央にある一の井戸は岩盤を堀り抜いたもので、深さ約16m(水深約8m)で、掘るのに2年もかかったと伝えれています。
 本丸跡に祀られている青山神社は3代将軍家光の養育係だった青山唯利と篠山城青山家4代目藩主忠裕が祭神です。
本丸跡に祀られている青山神社は3代将軍家光の養育係だった青山唯利と篠山城青山家4代目藩主忠裕が祭神です。
 天守台は本丸(天守丸)の南東部の城内で最も高く、奥まったところに位置し、天守台石垣は本丸内側からの高さ約4m、外側の南と東側犬走りからの高さ約18mで平面規模は東西約19m、南北約20m、約380㎡の広さです。築城時に天守閣は建てられませんでした。家康が、あまりに堅固な城となることを恐れ、つくらせなかったといいます。代わって、南東隅に二間四方(4m四方)単層の隅櫓を配置し、東面と南面に土塀を巡らせていました。東方には丹波富士と呼ばれる中世の山城である高城山(八上城跡)が美しい姿を見せています。
天守台は本丸(天守丸)の南東部の城内で最も高く、奥まったところに位置し、天守台石垣は本丸内側からの高さ約4m、外側の南と東側犬走りからの高さ約18mで平面規模は東西約19m、南北約20m、約380㎡の広さです。築城時に天守閣は建てられませんでした。家康が、あまりに堅固な城となることを恐れ、つくらせなかったといいます。代わって、南東隅に二間四方(4m四方)単層の隅櫓を配置し、東面と南面に土塀を巡らせていました。東方には丹波富士と呼ばれる中世の山城である高城山(八上城跡)が美しい姿を見せています。
 埋門から内堀を渡って三の丸へ。正面に本丸の石垣がをみることができ、石垣下で映画『レジェンド&バタフライ』の撮影が行われました。篠山城は一見すると平城のようですが、実は岩山を利用して築かれた平山城です。石垣で覆われているため、本来の地形が見えにくくなっていますが、本丸や内堀などでは岩盤の一部が顔をのじかせていて、篠山城の隠された姿を垣間見ることができます。
埋門から内堀を渡って三の丸へ。正面に本丸の石垣がをみることができ、石垣下で映画『レジェンド&バタフライ』の撮影が行われました。篠山城は一見すると平城のようですが、実は岩山を利用して築かれた平山城です。石垣で覆われているため、本来の地形が見えにくくなっていますが、本丸や内堀などでは岩盤の一部が顔をのじかせていて、篠山城の隠された姿を垣間見ることができます。
 南東側から見た目の前にそびえる天守台は、高さが約18mあり、篠山城で最も高い石垣です。篠山城の石垣は、慶長4年(1609)の築城の際に近江国の穴太衆の指導により築かれました。石垣の石材は篠山盆地の各所から運び込まれた野面石(自然石)と粗加工の割石が使われ、角部分は長方形の石を交互に積む算木積みという技法が用いられています。また石垣のいたるところに、くさびを打ち込んで石を割った痕跡である「矢穴」や多くの大名が参加した“天下普請”であることとを示す卍、◎、□、+など200種近い符号“刻印”が見られます。これは工事現場で争いを起し、家康の怒りを買うことを恐れた大名たちが、作業班ごとに刻印を決め、石に刻ませたと考えられています。
南東側から見た目の前にそびえる天守台は、高さが約18mあり、篠山城で最も高い石垣です。篠山城の石垣は、慶長4年(1609)の築城の際に近江国の穴太衆の指導により築かれました。石垣の石材は篠山盆地の各所から運び込まれた野面石(自然石)と粗加工の割石が使われ、角部分は長方形の石を交互に積む算木積みという技法が用いられています。また石垣のいたるところに、くさびを打ち込んで石を割った痕跡である「矢穴」や多くの大名が参加した“天下普請”であることとを示す卍、◎、□、+など200種近い符号“刻印”が見られます。これは工事現場で争いを起し、家康の怒りを買うことを恐れた大名たちが、作業班ごとに刻印を決め、石に刻ませたと考えられています。
 さらに南外濠を渡ると南馬出があります。篠山城の大きな特徴であり見所なのが、外濠側に設けられた三つの馬出です。馬出とは、防御力を高めるための戦闘用の出入り口の前面に築かれた離れ小島のようなスペースですが、南馬出のように土塁づくりの馬出が現在でも残っているのは篠山城だけです。他にも大手門の外側に大手馬出。東門の外側に東馬出が設けられていて、東馬出は馬出を囲む堀も残存しています。
さらに南外濠を渡ると南馬出があります。篠山城の大きな特徴であり見所なのが、外濠側に設けられた三つの馬出です。馬出とは、防御力を高めるための戦闘用の出入り口の前面に築かれた離れ小島のようなスペースですが、南馬出のように土塁づくりの馬出が現在でも残っているのは篠山城だけです。他にも大手門の外側に大手馬出。東門の外側に東馬出が設けられていて、東馬出は馬出を囲む堀も残存しています。
 薬研堀での鴛鴦の泳ぎに心を和ませながら篠山城の西外濠沿いの御徒士町武家屋敷群を歩く。慶長14年(1609)に篠山城が完成し、同時に城下の町割が行われました。御徒士町もその時に形成され城の西側の外濠に沿って南北の通りをつけ、西側に御徒士衆(藩主の警護役)を住まわせました。当時、割当てられた住宅は、間口が八間(14.5m)ありましたが天保元年(1830)の火災によって大部分が焼失しました。復興に際し、道路の西側は、屋敷を約6尺(約1.8m)後退させており、現存する徒士住宅の大部分のものは天保の火災後ほどなく建てられたものです。茅葺き入母屋造りで武者窓をつけた白壁の小林家長屋門、資料館として公開されている安間家ほか見応えある十数戸のお徒士衆の住宅が存在し、武家屋敷の面影をよくとどめ、土塀に囲まれた静かな佇まいは、今なお江戸時代末期の城下町の優れた歴史的景観を呈しています。
薬研堀での鴛鴦の泳ぎに心を和ませながら篠山城の西外濠沿いの御徒士町武家屋敷群を歩く。慶長14年(1609)に篠山城が完成し、同時に城下の町割が行われました。御徒士町もその時に形成され城の西側の外濠に沿って南北の通りをつけ、西側に御徒士衆(藩主の警護役)を住まわせました。当時、割当てられた住宅は、間口が八間(14.5m)ありましたが天保元年(1830)の火災によって大部分が焼失しました。復興に際し、道路の西側は、屋敷を約6尺(約1.8m)後退させており、現存する徒士住宅の大部分のものは天保の火災後ほどなく建てられたものです。茅葺き入母屋造りで武者窓をつけた白壁の小林家長屋門、資料館として公開されている安間家ほか見応えある十数戸のお徒士衆の住宅が存在し、武家屋敷の面影をよくとどめ、土塀に囲まれた静かな佇まいは、今なお江戸時代末期の城下町の優れた歴史的景観を呈しています。
 篠山城北側の二階町にあるのが篠山城築城の際、今の場所に遷座された篠山春日神社です。貞観年間(859~877)に藤原基経・時平父子が、奈良の春日大社の御分霊を当時の笹山に勧請したもので境内にある白鹿の石像が奈良・春日との関係を感じさせます。
篠山城北側の二階町にあるのが篠山城築城の際、今の場所に遷座された篠山春日神社です。貞観年間(859~877)に藤原基経・時平父子が、奈良の春日大社の御分霊を当時の笹山に勧請したもので境内にある白鹿の石像が奈良・春日との関係を感じさせます。
 絵馬殿に22面の絵馬が奉納されていて、中でも「黒神馬絵馬」は、絵から抜け出し畑の豆を食い散らかしたという伝説を持つほどの名作といわれています。同じ境内には文久元年(1861)能楽愛好者の藩主青山忠良によって建てられた能楽殿があり、当時箱根より西では最も立派なものといわれた舞台があります。普段は重厚な木の扉に閉ざされていますが、元旦の翁神事、4月に開催される春日能の年に2回だけ、その姿を見ることができます。小窓から中を覗くことが出来、松岡曾右衛門による立派な松の絵がちょっとだけ見える。床下には音響効果を高めるため、丹波焼の大甕が7個も埋められています。角度や深さなども厳密に計算されています。
絵馬殿に22面の絵馬が奉納されていて、中でも「黒神馬絵馬」は、絵から抜け出し畑の豆を食い散らかしたという伝説を持つほどの名作といわれています。同じ境内には文久元年(1861)能楽愛好者の藩主青山忠良によって建てられた能楽殿があり、当時箱根より西では最も立派なものといわれた舞台があります。普段は重厚な木の扉に閉ざされていますが、元旦の翁神事、4月に開催される春日能の年に2回だけ、その姿を見ることができます。小窓から中を覗くことが出来、松岡曾右衛門による立派な松の絵がちょっとだけ見える。床下には音響効果を高めるため、丹波焼の大甕が7個も埋められています。角度や深さなども厳密に計算されています。
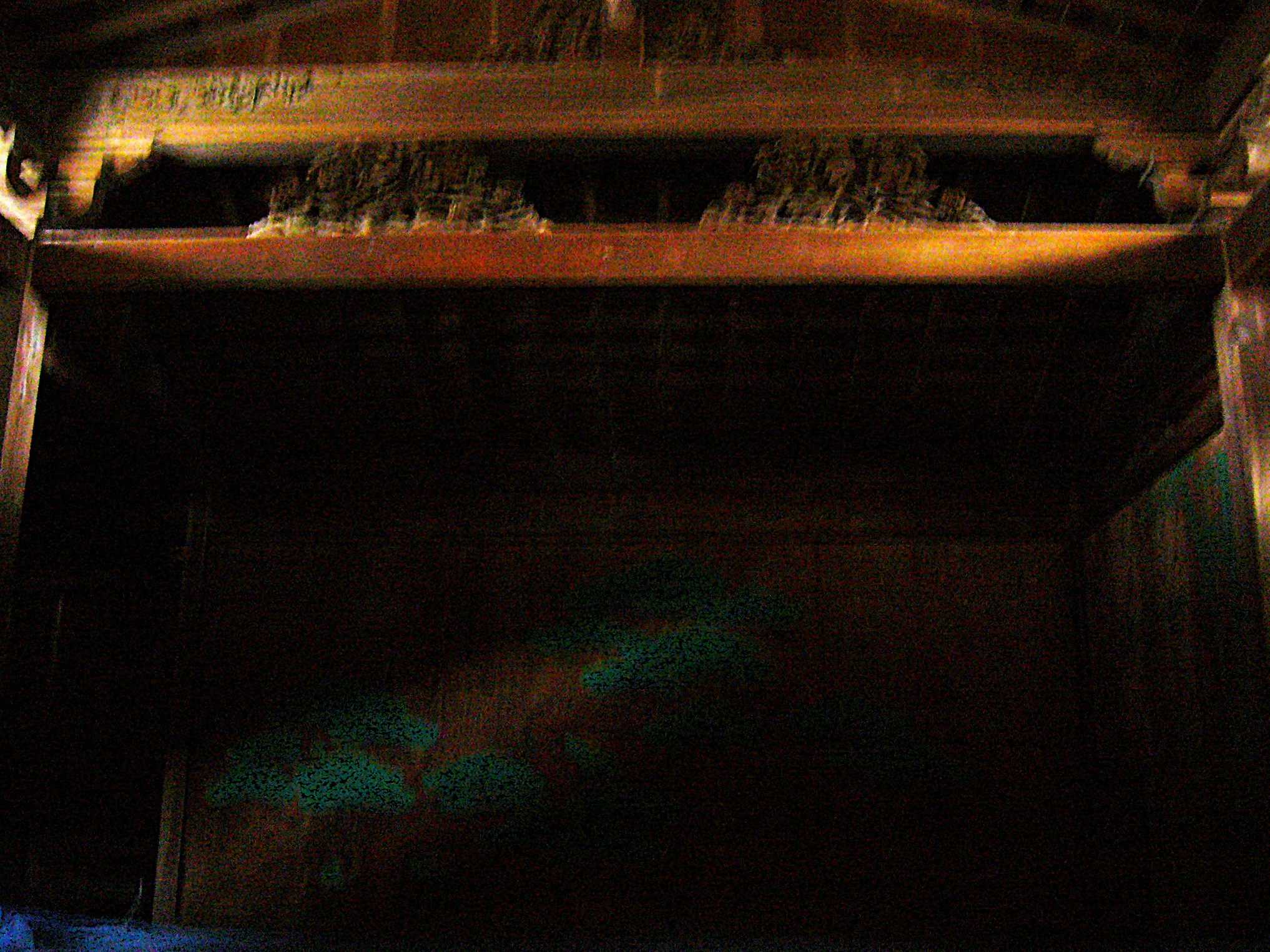 山に囲まれた盆地の篠山は、昼夜の寒暖の差が大きいことで、しばしば丹波霧といわれる霧が発生し、これが農作物にとってはこの上ない環境で、丹波栗、丹波黒豆、丹波の松茸と篠山はまさに美味の宝庫です。最近では篠山産の美味しい食材とお店のこだわりをまるごと味わうことが出来るを使ったユニークな「篠山まるごと丼」なるものがご当地グルメとして取り上げられているとのこと。しかしながらやはり蕎麦ということで、「波之丹州蕎麦処 一会庵」やミシュランにも掲載されている「ろあん松田」といった有名なお蕎麦やさんもありますがここは距離的にも近い丹波そば切り「花格子」さんに向かいます。
山に囲まれた盆地の篠山は、昼夜の寒暖の差が大きいことで、しばしば丹波霧といわれる霧が発生し、これが農作物にとってはこの上ない環境で、丹波栗、丹波黒豆、丹波の松茸と篠山はまさに美味の宝庫です。最近では篠山産の美味しい食材とお店のこだわりをまるごと味わうことが出来るを使ったユニークな「篠山まるごと丼」なるものがご当地グルメとして取り上げられているとのこと。しかしながらやはり蕎麦ということで、「波之丹州蕎麦処 一会庵」やミシュランにも掲載されている「ろあん松田」といった有名なお蕎麦やさんもありますがここは距離的にも近い丹波そば切り「花格子」さんに向かいます。
篠山城東側、約600m、三角形の屋根や茅葺きの商家が続く、河原町通は名前も雰囲気も、どこか京都に似ているような気がします。このあたりは河原町妻入商家群と呼ばれ、篠山城築城の際に作られた城下町篠山の商業の中心として大変栄えた古い街並みで、妻入り商家が軒を連ねる。妻入りとは、屋根に対して直角の面に出入り口がある家のことで、5~8mほどの間口は狭いが、奥行きは大半が40m以上もある鰻の寝床のような間取りになっています。表構えの大戸、千本格子や荒格子、中二階の出格子、虫籠窓さらに風防・防火の役割を持つうだつなど、江戸時代の旧街道の街並みの面影を今に伝え国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。
 そんな一角にお目当ての「花格子」がある。妻入商家の建物の暖簾をくぐると、入口から入ってすぐ右手には座敷席があり、奥には4人掛けのテーブル席。中は日本家具といっしょにぐい飲みや切り絵などが配置され、入口すぐの黒板にはお勧めのメニューが書かれています。もとは和食の料理人をされていたのか一品料理が充実。北海道、福井、島根、鳥取など納得のいく風味豊かな原料を毎朝石臼で甘皮ごと挽いて、蕎麦を打つ。
そんな一角にお目当ての「花格子」がある。妻入商家の建物の暖簾をくぐると、入口から入ってすぐ右手には座敷席があり、奥には4人掛けのテーブル席。中は日本家具といっしょにぐい飲みや切り絵などが配置され、入口すぐの黒板にはお勧めのメニューが書かれています。もとは和食の料理人をされていたのか一品料理が充実。北海道、福井、島根、鳥取など納得のいく風味豊かな原料を毎朝石臼で甘皮ごと挽いて、蕎麦を打つ。
 お勧めはほんのり甘い香りの喉越しの良い蕎麦と黒豆笹おこわとがセット(小鉢付)になったそば膳。今日は入口でみた好評の坂越の牡蠣の天ぷら今年も入荷780円と牡蠣の天ぷら付染めおろし蕎麦(温)1380円の貼り紙が目に焼き付いていたので、冷えた体と牡蠣の天ぷらの欲望に勝てず、これにをセットにして頼むことにした。最初にそばの端っこを揚げたそば煎餅がお茶と一緒に運ばれてきたのですが、これが香ばしい味わい。そして次に、冷たい細切りの十割そばに熱いだし汁をかけその上に紅葉おろしときざみ葱、そして坂越の牡蠣の天ぷらが2個載った椀と小鉢と黒豆笹おこわが運ばれてきました。坂越は播州赤穂の先にある「都市景観100選」にも選ばれている港町でミネラル豊富で、手付かずの自然が残る播磨灘の牡蠣はたった一年で出荷できるまで大きく立派に成長し、身が柔らかく、縮みにくいのが特徴です。
お勧めはほんのり甘い香りの喉越しの良い蕎麦と黒豆笹おこわとがセット(小鉢付)になったそば膳。今日は入口でみた好評の坂越の牡蠣の天ぷら今年も入荷780円と牡蠣の天ぷら付染めおろし蕎麦(温)1380円の貼り紙が目に焼き付いていたので、冷えた体と牡蠣の天ぷらの欲望に勝てず、これにをセットにして頼むことにした。最初にそばの端っこを揚げたそば煎餅がお茶と一緒に運ばれてきたのですが、これが香ばしい味わい。そして次に、冷たい細切りの十割そばに熱いだし汁をかけその上に紅葉おろしときざみ葱、そして坂越の牡蠣の天ぷらが2個載った椀と小鉢と黒豆笹おこわが運ばれてきました。坂越は播州赤穂の先にある「都市景観100選」にも選ばれている港町でミネラル豊富で、手付かずの自然が残る播磨灘の牡蠣はたった一年で出荷できるまで大きく立派に成長し、身が柔らかく、縮みにくいのが特徴です。
 この天ぷらが絶品であった。適度にだし汁を吸った衣とぎりぎりのタイミングで揚げた丸々と太った牡蠣のぷりぷりとした食感がベストマッチ。お蕎麦もしっかりとコシがあり咽越しも良く、蕎麦湯もそば粉を溶いたもので至福の時間でした。。
この天ぷらが絶品であった。適度にだし汁を吸った衣とぎりぎりのタイミングで揚げた丸々と太った牡蠣のぷりぷりとした食感がベストマッチ。お蕎麦もしっかりとコシがあり咽越しも良く、蕎麦湯もそば粉を溶いたもので至福の時間でした。。
近くには平安遷都を前に、王城候補地の一つに選ばれたことから「王地山」との名前が付けられた、七尾七谷といわれる桜と紅葉の名所・王地山公園に「王地山まけきらい稲荷」が鎮座します。公園のふもとから約200段ある石段に沿って並ぶ赤い鳥居をくぐり抜けると別名「まけきらい稲荷」と呼ばれる王地山平左衛門稲荷にたどり着きます。その昔、青山忠裕公が藩主の時代、篠山領内のお稲荷さんが力士に姿を変え、将軍上覧の大相撲に連勝し、藩主を喜ばせたという言い伝えがあり、そのお相撲さんの名が王地山平左衛門で、今でも招福除災・商売繁盛、勝利守護、また合格成就の神として広く信仰されているのである。
 王地山公園には隣接する温泉宿「ささやま荘」の天然温泉「王地山まけきらいの湯」があり、大浴場や露天風呂、サウナを備え、幅広い効能を誇る含放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉のアルカリ性の良泉が満喫できます。
王地山公園には隣接する温泉宿「ささやま荘」の天然温泉「王地山まけきらいの湯」があり、大浴場や露天風呂、サウナを備え、幅広い効能を誇る含放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉のアルカリ性の良泉が満喫できます。












